最近、「薄毛をカバーする帽子」をつい手に取りたくなる日が増えていませんか?
実はその裏側に、ヘアカラーが原因の頭皮トラブルが潜んでいることもあるんです。
とくに「カラー後にかさぶたができて痛い」「薄毛をカバーする帽子に頼りっぱなし」という方は、ぜひこの記事を読んでみてください。
敏感肌やアレルギー体質の方でも安心して使えるカラーの選び方や、かさぶたになった頭皮のケア方法を、わかりやすくご紹介しています。
 Aya
Aya寝起きの爆発ヘア、もう鏡の前で凍りつかない!1日1回のリデン習慣で、天使のツヤ髪へ
(心の声:朝イチでこの髪…会社や学校行きたくない…)
男女兼用の本気の育毛剤
今なら13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー
→ 詳しく見る
- ヘアカラー後に頭皮にかさぶたができる主な原因と仕組みを解説
- 自然治癒の見極め方と皮膚科に行くべき判断ポイントを紹介
- ゼロテクやノンジアミンカラーなど、頭皮にやさしい選択肢を提案
- 洗い方・保湿ケア・トリートメントの正しい使い方まで丁寧に解説
ヘアカラー後に頭皮がかさぶたになる原因とは?|薬剤と皮膚反応の仕組みを解説
ヘアカラーをしたあと、頭皮にかさぶたができてしまった経験はありませんか?
これは決して珍しいトラブルではなく、実は多くの人が知らずに繰り返してしまっている頭皮への刺激が原因で起こる現象です。
特に自宅でカラーリングをしている方や、美容室でも薬剤選びが適切でなかった場合に起こりやすくなります。
そもそも、ヘアカラー剤にはアルカリ剤や過酸化水素、水酸化アンモニウムなど、皮膚にとっては強い刺激となる成分が含まれています。
これらが頭皮に直接触れると、皮膚のバリア機能が壊れ、軽度の炎症から始まり、やがて「接触性皮膚炎」や「アレルギー性皮膚炎」に発展することがあります。
すると、炎症の治癒過程で皮膚表面にかさぶたが形成されるのです。
とくに乾燥肌や敏感肌の方、また季節的に空気が乾燥している冬場などは、頭皮環境が不安定になりやすいため、こうしたトラブルが起こりやすくなります。
そのうえ、同じカラー剤を繰り返し使用していると、蓄積された刺激によりアレルギー症状を引き起こすリスクも高くなるため注意が必要です。
また、頭皮にかさぶたができた状態でカラーを続けてしまうと、皮膚の再生が追いつかず、かゆみや慢性的な炎症を招くことにもつながります。
したがって、症状を放置せず、早めに対処することが大切です。
このように、頭皮にかさぶたができる原因には薬剤の刺激だけでなく、肌質や環境、体調なども複雑に関係しています。
それでは次に、実際にかさぶたができてしまった場合にどうケアすれば良いのかを見ていきましょう。
“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本
今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
かさぶたができた頭皮をどうケアすべき?|やって良いこと・NG行動

ヘアカラー後に頭皮にかさぶたができてしまうと、とても不安になりますよね。
見た目ではよく分からない場所なだけに、「このまま放っておいても大丈夫かな」と感じたり、「つい気になって触ってしまう」という方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、頭皮のかさぶたは皮膚がダメージから回復しようとする大切なプロセスの一部です。
したがって、無理にはがしたり、間違ったケアをしてしまうと、かえって症状を悪化させてしまうことがあるんです。
まず大切なのは、「触らない」「引っ掻かない」「無理に取らない」という基本の三原則を守ることです。
これは、お子さんのかさぶたと同じように考えていただくと分かりやすいと思います。
たとえば、転んで膝にできたかさぶたを気にして剥がしてしまうと、なかなか傷が治らなかったり、跡が残ってしまうことってありますよね。
頭皮でも同じことが言えるのです。
とくに髪の毛の生え際や分け目にできたかさぶたは、ついシャンプーのときにゴシゴシ洗ってしまったり、ドライヤーで熱風を当てすぎてしまったりと、刺激を与えやすい場所でもあります。
そのため、ケアの際には「優しさ第一」を心がけてみてください。
具体的な方法としては、まずシャンプー選びを見直すことがポイントです。
よくある市販の洗浄力が強いシャンプーでは、頭皮に必要な皮脂まで落としてしまい、さらに乾燥や刺激を引き起こす原因になります。
できれば、アミノ酸系やベビーシャンプーなど、低刺激で保湿力の高い製品を選ぶようにしましょう。
また、洗髪時には爪を立てずに指の腹でやさしくマッサージするように洗うと安心です。
泡立ちが足りないときは、手でしっかり泡立ててから髪と頭皮にのせるようにすると、摩擦を最小限にできます。
そして、すすぎも丁寧に行うことが大切です。
シャンプーやコンディショナーのすすぎ残しがあると、それ自体が刺激になってしまい、せっかく回復しかけている頭皮に余計な負担をかけてしまいます。
なお、洗髪後のドライヤーも注意が必要です。
ドライヤーを近づけすぎたり、熱風を1か所に当て続けると、それが新たな刺激になってしまいます。
できれば15~20cm程度離して、頭皮ではなく髪の根元を中心に風を当てるようにしましょう。
一方で、やってはいけないNG行動もいくつかあります。
たとえば、ヘアオイルや育毛剤などを「かさぶたの上から塗る」という行為は、いかにも良さそうに見えて実は逆効果です。
なぜなら、まだ皮膚が炎症を起こしている状態にさらに異物を与えることで、かゆみや炎症を助長してしまうことがあるからです。
また、頭皮マッサージも注意が必要です。
たしかに血行促進には良いとされていますが、かさぶたがある部分に刺激を与えることで、かさぶたがはがれてしまったり、雑菌が入ってしまうリスクがあります。
ですので、完全に治るまでは控えるほうが安心です。
ちなみに、私自身も以前セルフカラーをした後にかさぶたができてしまったことがあるのですが、薬局で売られている「非ステロイド系の頭皮用保湿ローション」でやさしく保湿を続けたところ、1週間ほどで自然に治りました。
もちろん個人差はありますが、焦らずに「頭皮の回復力を信じて見守る」ことも大切なのだと感じました。
このように、正しいケア方法を知っておくだけで、頭皮のトラブルはぐんと回復に向かいやすくなります。
とはいえ、自己判断だけでは不安なこともあると思いますので、次は「自然に治るのか、それとも皮膚科に行くべきか」の見極めポイントについて見ていきましょう。
染めた後のかさぶた、自然に治る?皮膚科に行く判断基準とは
ヘアカラーのあとに頭皮にかさぶたができると、「このまま自然に治るのかな?」「病院に行くほどではないかも」と迷ってしまいますよね。
私自身も、過去に市販のカラー剤を使って染めた翌日、耳の上あたりがピリピリしてかさぶたになったことがあり、「これは様子を見るべきか、すぐに皮膚科に行くべきか」とかなり悩んだ経験があります。
そこでまずお伝えしたいのは、軽度のかさぶたで、かゆみや痛みが強くない場合は、数日から1週間程度で自然に治ることも多いということです。
たとえば、赤ちゃんが引っかいてできた小さなかさぶたが、何もせずにいつの間にか取れていた、というようなことがありますよね。
それと同じように、刺激を受けた頭皮も、肌の再生サイクルが順調であれば、自力で修復してくれる力を持っています。
しかしながら、すべてのケースで「放置していれば大丈夫」とは言い切れません。
では、どのような場合に皮膚科を受診すべきなのでしょうか?
ひとつの目安は、「かさぶたの範囲」と「症状の強さ」です。
たとえば、
・かさぶたの範囲が広い
・赤みや腫れがどんどん広がっている
・痛みやかゆみが強くて眠れないほど
・浸出液(じくじくした液体)が出てきている
・治りかけてもまたすぐに再発する
といった症状がある場合は、自己判断ではなく、皮膚科での診察をおすすめします。
なぜなら、これらの症状は単なる一時的な炎症ではなく、「アレルギー性接触皮膚炎」や「細菌感染」など、治療が必要な状態に進行している可能性があるからです。
ちなみに、アレルギー性接触皮膚炎は、初回では何ともなくても、数回目以降で突然発症することがあります。
そのため、「前は同じカラー剤で大丈夫だったのに、今回はひどくなった」という場合も注意が必要です。
更には、体調が不安定だったり、免疫力が低下しているときは、普段は平気な刺激にも敏感に反応してしまうことがあります。
実際、私の知人も、産後まもなくセルフカラーをしたところ、頭皮全体にかゆみとかさぶたが広がってしまい、皮膚科でステロイド系の塗り薬を処方されていました。
医師によると、ホルモンバランスの変化も肌トラブルの一因になるとのことでした。
また、皮膚科では、かさぶたの状態を見て薬の選択だけでなく、アレルギー検査を勧められることもあります。
特に「パラフェニレンジアミン(通称:ジアミン)」という成分に反応している方が多く、ジアミンアレルギーがあると今後は一般的なカラー剤の使用を避けなければなりません。
よって、もし同じようなトラブルを何度か経験されている方は、一度アレルギーの有無を調べておくと安心です。
なお、皮膚科に行くか迷ったときは、市販薬を使ってみるのもひとつの方法ですが、注意点もあります。
たとえば、「頭皮の保湿ローション」や「かゆみ止めの塗り薬」などを使う場合でも、傷口が開いていたり、ジュクジュクしているときには使用を避けるべきものもあります。
ですので、成分表をよく確認し、可能であれば薬剤師さんに相談することをおすすめします。
このように、かさぶたの程度や症状の強さによって対応は異なりますが、頭皮は顔と同じくらいデリケートな部分なので、「様子を見る」にも限界があります。
だとすると、繰り返さないための対策がとても大切になってきますね。
次は、カラーによる頭皮ダメージをどう防いでいくか、美容師さんの工夫や選び方についてご紹介します。
繰り返すカラーによる頭皮ダメージを防ぐには?|美容師が教える工夫と選び方

ヘアカラーをするたびに頭皮に違和感があったり、かさぶたやかゆみが毎回出てしまう方にとっては、「カラー=我慢するもの」になってしまっているかもしれません。
しかし、実際にはちょっとした工夫や選び方を変えるだけで、頭皮への負担を大きく減らすことができます。
たとえば、美容院で「ゼロテク」という技術をご存じでしょうか?
ゼロテクとは、カラー剤を頭皮に直接つけず、ギリギリのところから塗布する方法で、美容師さんが特別なコームテクニックを使って施術します。
この方法なら、頭皮への刺激を大幅に減らすことができるため、繰り返しカラーをしている方や敏感肌の方にはとても効果的です。
実際に私の友人も、以前は毎回カラーの後に頭皮がピリピリしていたのですが、ゼロテクに変えてからは「あれ?今日は平気かも」と言うようになりました。
しかも、発色も綺麗なままで染められるので、仕上がりも満足できたようです。
では、自宅でセルフカラーをしている場合はどうすればいいのでしょうか。
まず、セルフカラーの場合でも、できるだけ頭皮に薬剤がつかないように塗布する工夫が必要です。
たとえば、カラーリング前に「頭皮保護クリーム」を使うのも一つの方法です。
これは美容室でも使われているもので、ワセリンのような質感のクリームを分け目や生え際など、刺激を感じやすい部分に塗っておくと、薬剤の浸透を和らげてくれます。
また、コームやブラシを使って丁寧に塗ることでも、頭皮への接触を最低限に抑えることができます。
とはいえ、染め方だけでなく、使用するカラー剤そのものも見直すことが大切です。
ドラッグストアで手に入るカラー剤の多くは、誰でも簡単に使えるように強めの薬剤が使われている傾向にあります。
したがって、肌が弱い方やトラブルを繰り返している方は、「ノンジアミンカラー」や「ヘアマニキュア」「ヘナカラー」など、より低刺激な選択肢を検討してみてください。
ちなみに、ジアミンとは酸化染料の一種で、ヘアカラーによるアレルギーの原因となることが多い成分です。
美容室では、ノンジアミンカラーに切り替えることでトラブルを回避できたお客様が多く、特に「かさぶたができやすい方にはおすすめですよ」と美容師さんがおっしゃっていました。
更には、カラーの頻度を見直すことも頭皮を守るポイントになります。
たとえば、根元のリタッチだけで済ませる回を増やす、暗めのカラーを選んで退色しにくくする、カラートリートメントを活用するなど、髪全体を染める頻度を減らすことで、頭皮へのダメージも少なくなります。
尚、カラー後のケアもとても重要です。
染めたあとの頭皮はとても敏感になっているため、当日はなるべく湯船につからずシャワーのみにし、保湿を意識したシャンプーとトリートメントを使ってやさしくケアすることが大切です。
たとえば、ヒアルロン酸やセラミドなどが含まれている保湿系シャンプーを選ぶと、乾燥や刺激を抑えられます。
また、頭皮の乾燥を防ぐためには、ドライヤー後に「頭皮用ミスト」などで軽く保湿をしてあげるのもおすすめです。
むしろ、髪だけでなく頭皮もスキンケアと同じように考えてあげると、トラブルが起きにくくなるかもしれません。
このように、美容室での施術方法・使う薬剤・日々のケアなど、いくつかのポイントを工夫することで、カラーと上手に付き合っていくことができます。
それでは次に、敏感肌やアレルギー体質の方でも安心してヘアカラーを楽しむための選び方について、詳しくお話ししていきます。
敏感肌・アレルギー体質でもできる安心カラーの選び方
敏感肌やアレルギー体質の方にとって、ヘアカラーは少し勇気がいるものかもしれません。
「おしゃれはしたいけれど、かゆみや赤みが出てしまったらどうしよう」と不安に感じること、きっとありますよね。
実際に、私の友人にも、カラー剤で毎回頭皮がかゆくなってしまうという悩みを抱えていたママがいます。
そこで今回は、そういった方でも安心してカラーを楽しめる方法について、いくつかの視点からお話ししていきたいと思います。
まず、最も大切なのは「自分に合ったカラー剤を選ぶ」ことです。
というのは、カラー剤にはいろいろな種類があり、それぞれ配合されている成分や作用の強さが異なるからです。
特に敏感肌の方にとって避けたいのが、「ジアミン系染料」を含むカラー剤です。
ジアミンは発色が良く、長持ちするというメリットがある一方で、アレルギー反応を起こしやすい成分としても知られています。
よって、かゆみや赤み、かさぶたなどの症状が出たことがある方は、ノンジアミンタイプのカラー剤を選ぶのが安心です。
たとえば、美容室でも取り扱いのある「ノンジアミンカラー」や「オーガニックカラー」は、敏感肌対応として開発されており、頭皮への刺激が少なくなるよう工夫されています。
また、「ヘアマニキュア」も頭皮に薬剤が触れにくいため、比較的刺激が少なく済むカラー方法のひとつです。
ただし、ヘアマニキュアは表面をコーティングするように色をつけるため、発色や持続力の面で物足りなさを感じる方もいるかもしれません。
ですが、その分頭皮への負担が減ると考えると、選ぶ価値は十分にあります。
ちなみに、植物由来の「ヘナカラー」も人気ですが、天然成分だからといって誰にでも合うわけではありません。
たとえば、ナチュラルヘナは問題がなくても、化学染料が混ざったヘナ製品ではアレルギー反応が出ることもありますので、成分表示をしっかり確認してから使うことが必要です。
更には、パッチテストの重要性も見逃せません。
特にアレルギー体質の方や過去にトラブルがあった方は、カラー剤を使用する48時間前には必ずパッチテストを行ってください。
腕の内側や耳の裏などに少量塗布して、赤みやかゆみが出ないか確認することで、予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。
なお、美容室でのカラーを検討されている方は、事前にカウンセリングを受けて「肌が敏感であること」や「アレルギー歴があること」をしっかり伝えるようにしましょう。
信頼できる美容師さんであれば、使用する薬剤や塗布の仕方を工夫して、できるだけ刺激が少ない方法を提案してくれるはずです。
一方、自宅でセルフカラーをする場合は、「頭皮に薬剤をつけないようにする」工夫も大切です。
たとえば、頭皮保護用のクリームを生え際や分け目に塗っておく、専用のコームで根本から少し浮かせて塗るなど、小さな工夫が頭皮トラブルの予防につながります。
また、カラー後のケアにも気を配ることが大切です。
染めたあとの頭皮はバリア機能が弱まっているため、低刺激で保湿力のあるシャンプーやトリートメントを使って、やさしく洗ってあげることが重要です。
例えるなら、顔に軽い日焼けをしたあとに、しっかり保湿してあげるような感覚ですね。
このように、肌の状態や体質に応じてカラー剤の種類を選び、前後のケアを丁寧に行うことで、敏感肌でも安心してヘアカラーを楽しむことができます。
それでは最後に、カラー後の敏感な頭皮において「シャンプーやトリートメントはどうするべきか」という、実践的なケア方法について見ていきましょう。
【番外編】頭皮にかさぶたができたらシャンプーやトリートメントはどうすればいい?
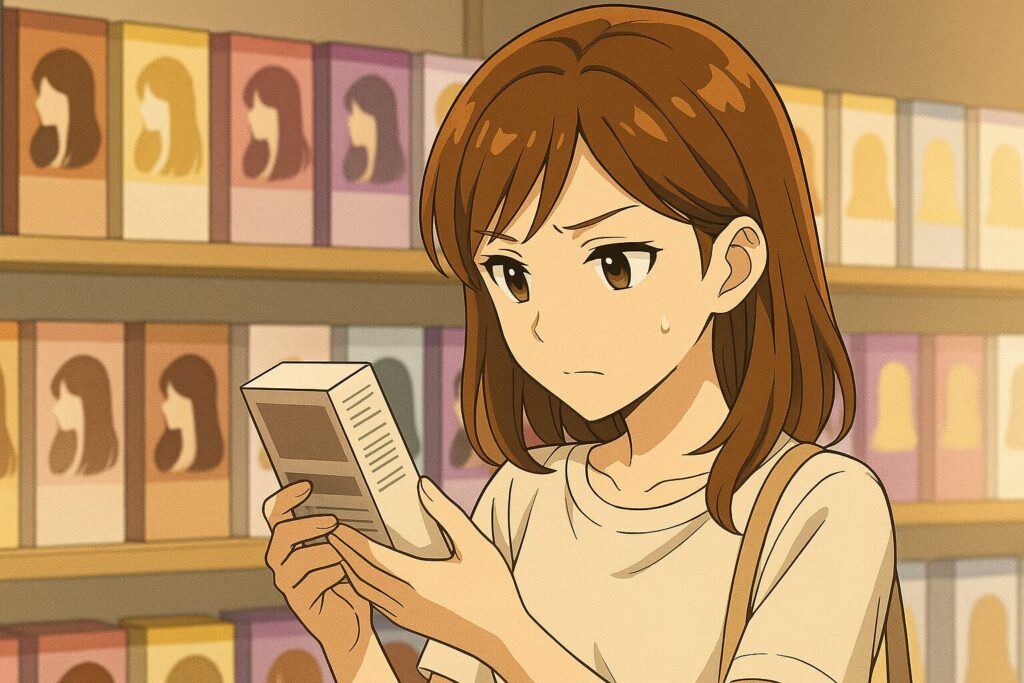
頭皮にかさぶたができてしまったとき、毎日のシャンプーやトリートメントをどうしたらいいのか、正直とても悩みますよね。
「洗わなければ不衛生かもしれないし、でも洗ったら悪化しそう」と、どちらを優先すべきか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
実際、私も以前にカラー後のかゆみでかさぶたができてしまったとき、普段通りにシャンプーをしてしみてしまった経験があります。
その痛みがトラウマのようになってしまって、次に同じ状況になったときには、洗うことに慎重になったのを今でも覚えています。
では、かさぶたがある状態のときにどのようなケアが最善なのでしょうか。
まず大前提として、頭皮は毎日少しずつ皮脂や汗を分泌していますので、過度に洗うのを避けながらも、ある程度は清潔に保つ必要があります。
だからといって、通常通りのシャンプーを使ってゴシゴシ洗ってしまうのは逆効果です。
かさぶたがはがれてしまったり、炎症を悪化させてしまう原因になります。
したがって、使用するアイテム選びと洗い方の見直しがとても重要になります。
たとえば、洗浄力の強い石油系シャンプーは刺激が強すぎることがありますので、アミノ酸系やベビーシャンプーのような低刺激処方の製品がおすすめです。
こういったシャンプーは、頭皮の皮脂バランスを崩しにくく、かつ必要なうるおいは残しながら洗浄できるため、肌トラブルが起きているときにも安心して使えます。
また、泡立てにもひと工夫すると、さらに頭皮への刺激を減らすことができます。
直接頭にシャンプーを乗せるのではなく、手のひらでしっかり泡立ててから、ふわっと泡をのせるようにして洗うのがポイントです。
例えるなら、顔を洗うときの泡洗顔と同じイメージで、摩擦をできるだけ少なくすることが大切です。
指の腹を使ってやさしくマッサージするように洗い、絶対に爪を立てたり、ゴシゴシと強くこすったりしないよう注意してください。
すすぎの際も、ぬるま湯をたっぷり使って、洗い残しがないように丁寧に流すことが重要です。
シャンプーやトリートメントの成分が残ってしまうと、それ自体が刺激となってしまうことがあります。
ちなみに、湯温も大切なポイントです。
熱すぎるお湯は頭皮を乾燥させてしまう原因になりますので、38度前後のややぬるめのお湯で優しく洗い流してあげてください。
一方で、トリートメントについては少し注意が必要です。
というのは、トリートメントは基本的に髪に栄養や保湿を与えるものですが、頭皮につけてしまうと毛穴に詰まりやすく、かさぶたや炎症を悪化させる可能性があるからです。
そのため、かさぶたがあるときは、トリートメントを髪の中間から毛先のみに使用し、頭皮には絶対に付かないようにしてください。
また、頭皮が乾燥しがちな方は、ドライヤー後に「頭皮用ローション」や「スカルプミスト」などで保湿するのもおすすめです。
ただし、かさぶたの状態によっては、医師に相談したうえで使用するほうが安心な場合もあります。
尚、ドライヤーを使うときは、距離をしっかりとって、風を分散させながら乾かすのがコツです。
1か所に熱風が集中すると、それだけで刺激になってしまいますので、時間をかけてやさしく乾かしてあげるようにしてください。
このように、シャンプーやトリートメントを使うときには「どの製品を選ぶか」「どのように使うか」がとても大切になります。
そして、日々のケアを見直すことで、カラー後の頭皮トラブルは予防できるようになるかもしれません。
それでは最後に、この記事全体を通して、カラーによる頭皮かさぶたトラブルへの正しい理解と対処法について、やさしくまとめていきます。
まとめ
ヘアカラーのあとに頭皮にかさぶたができてしまうと、すごく不安になりますよね。
私も初めて経験したときは、「これって大丈夫なのかな」「もうカラーできないかも」って本気で悩みました。
だけど、ちゃんと原因を知って、正しいケアやカラー剤の選び方をすれば、トラブルは防げるんだなって感じました。
特に、頭皮に直接つかないように工夫する「ゼロテク」や、ノンジアミンカラーのような低刺激の薬剤を選ぶことってすごく大切なんですよね。
それに、もし頭皮がトラブルを起こしてしまっても、正しい洗い方やトリートメントの使い方を知っておくと、悪化させずに回復を待つことができるので安心です。
もちろん、かさぶたの範囲が広かったり、かゆみがひどいときは無理せずに皮膚科の先生に相談してくださいね。
私たちママ世代は、忙しさの中でつい自分のことは後回しにしがちですが、髪や頭皮の健康って、気持ちにまで影響する大事なものだと思います。
だからこそ、無理をせず、やさしいケアと選び方で、自分に合ったカラーライフを楽しんでいきたいですね。
“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本
今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
参考記事
