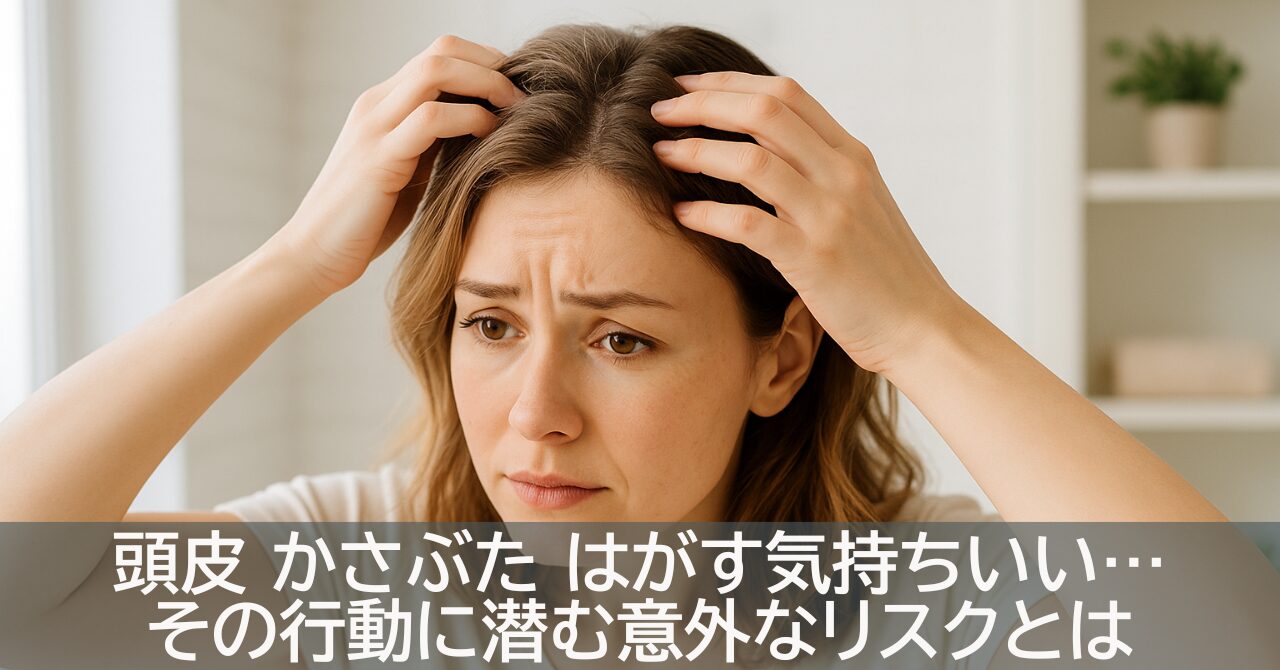頭皮のかさぶたを剥がすと、なぜか「気持ちいい」と感じてしまう。
そんな経験、ありませんか?
私自身も、ストレスが溜まったときや、なんとなく手持ち無沙汰なときに、つい頭を触ってしまっていました。
でも、その気持ちよさの裏には、思わぬリスクや悪循環が隠れているんです。
このページでは、「頭皮 かさぶた はがす 気持ちいい」と検索した方の疑問や不安をやさしく解消し、今日からできる対策やケア方法を丁寧にお伝えしていきます。
 Aya
Aya「“最近疲れてる?”って言われたその理由、頭皮だったかも。」
(心の声:髪があるだけで、こんなに若く見えるなんてズルい…)
男女兼用の本気の育毛剤
今なら13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー
→ 詳しく見る
- 頭皮のかさぶたを剥がす心理と、その快感の理由をやさしく解説
- 剥がすことで起きるリスクと悪循環を具体例で紹介
- かさぶたを防ぐ頭皮ケアや生活習慣をわかりやすく提案
- 無理せず癖をやめるための実践的なアドバイスを掲載
頭皮のかさぶたを剥がすと気持ちいい?その心理的な背景とは
頭皮にできたかさぶたを、つい無意識にはがしてしまうことってありませんか?
しかも、それが「なんだか気持ちよく感じてしまう」こともあり、不思議に思ったことがある方も多いと思います。
この行動、実は多くの人が経験していることで、精神的な側面と深く関係しているんです。
たとえば、小さいころ転んでできたひざのかさぶたを、治りかけのときについつい剥がしてしまった…という経験、思い出せませんか?
これは、身体的な快感というよりも「不安やストレスからくる無意識の行動」の一種と考えられています。
心理学では「抜毛症」や「皮膚むしり症」といったカテゴリーに分類されることもあり、無意識に皮膚をいじることで一時的な安心感を得ようとしているのです。
特に、ストレスや不安、過度な緊張があると、指先を動かす癖が出やすくなると言われています。
頭皮は目に見えにくい部分でもあるため、「今、誰にも見られていないからついやってしまう」という心理も働きやすいんですね。
また、かさぶたを剥がすことで、「汚れが取れた」「スッキリした」といった感覚を得られるため、クセになりやすいのです。
これは、いわば“擬似的な達成感”とも言えるでしょう。
しかしながら、ここに落とし穴があります。
一時的な快感の代償として、皮膚がさらに傷ついてしまい、治癒に時間がかかったり、かえってフケが増えたり、頭皮が炎症を起こすなど、無意に悪化させるリスクが高まってしまいます。
そのため、医師や皮膚科でも「かさぶたは自然に剥がれるまで触らないこと」が基本の治療指導とされています。
ちなみに、私の友人も以前、脂漏性皮膚炎が原因で頭皮にかさぶたができていた時期がありました。
最初は「なんかポロポロ取れて気持ちいい」と笑っていたんですが、繰り返すうちにかゆみや赤みが悪化して皮膚科を受診することになりました。
医師に言われたのは、「指で剥がすほど治りが遅くなる」というシンプルだけど大切な事実でした。
ですから、もしあなたも「頭皮のかさぶたを剥がすと気持ちいい」と感じていたら、その背後にある心のサインにも少しだけ目を向けてみてくださいね。
では次に、頭皮のかさぶたを剥がすことのリスクと悪循環について、より詳しく見ていきましょう。
“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本
今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
頭皮のかさぶたを剥がすことのリスクと悪循環

頭皮にできたかさぶたを剥がすと、つい「スッキリした」「つるっとした感触が気持ちいい」と感じてしまうことがあります。
しかしながら、それが繰り返されるうちに、知らず知らずのうちに頭皮の健康を損ねてしまっている可能性があるんです。
たとえば、かさぶたを無理に剥がすという行為は、ちょうど“ふやけた絆創膏をはがすようなもの”だと考えてみてください。
表面はきれいになったように見えても、その下の皮膚はまだ完全に治っておらず、刺激にとても弱い状態です。
だからこそ、無理に剥がしてしまうことで皮膚のバリア機能が壊れ、余計に傷つき、さらに新しいかさぶたをつくる…という悪循環に陥りやすくなるのです。
この悪循環が続くと、頭皮は「治癒と破壊」を繰り返すことになり、最終的には慢性的な炎症やフケ、かゆみ、さらには抜け毛などのトラブルにまで発展してしまうことがあります。
また、かさぶたができる背景には、脂漏性皮膚炎などの皮膚疾患が隠れていることも少なくありません。
脂漏性皮膚炎は、皮脂の分泌が多く、そこに常在菌であるマラセチア菌が過剰に繁殖してしまうことで炎症が起き、結果としてかさぶたや赤み、かゆみが生じる病気です。
このような皮膚の病気が原因でかさぶたができている場合、自己判断で剥がすことで症状をこじらせてしまうおそれがあります。
ですので、繰り返す頭皮のかさぶたやフケが気になる場合は、なるべく早めに皮膚科を受診して、医師による正しい診断と治療を受けることが大切です。
たとえば、私の知人には、長い間「乾燥によるフケ」と思い込んで市販の保湿シャンプーだけで対処していた方がいました。
しかし実際には脂漏性皮膚炎だったことがわかり、皮膚科で処方された抗真菌シャンプーと外用薬を使うようになってからは、1ヶ月もしないうちにかさぶたやかゆみがぐんと減ったそうです。
このように、「かさぶたをはがしてしまう癖」の裏には、そもそもの原因を見落としているケースも少なくありません。
なお、癖になっている場合は、ふとしたタイミングでつい指が頭にいってしまい、無意識のうちにかさぶたを探してしまう方も多いと思います。
そのようなときは、手鏡で頭皮の状態を確認したり、保湿ミストなどを使って「触るかわりにケアする」習慣を取り入れると、無意識の癖を意識的な行動に変えていけるかもしれません。
ちなみに、私も以前、ストレスが多かった時期に頭皮に小さなかさぶたを見つけては、寝る前につい剥がしてしまっていたことがありました。
当時はただの癖だと思っていたのですが、かさぶたが治りきらないまま何度も傷になってしまい、髪の分け目周辺の毛が少し薄く見えるようになって、初めて危機感を抱きました。
そこから皮膚科に相談し、かさぶたの原因が乾燥と摩擦によるものであるとわかって、保湿ローションを使うようになってからはだいぶ改善しました。
ですので、もしも今「かさぶたを剥がすことがやめられない」と感じている方がいらっしゃったら、それは体からのSOSのサインかもしれません。
次に、そうした癖をやめたいときにどうすれば良いか、具体的な方法を一緒に見ていきましょう。
頭皮にかさぶたができる主な原因とは
かさぶたというと、転んだときの傷にできるものを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、頭皮にできるかさぶたには少し違ったメカニズムがあります。
というのは、頭皮は髪の毛に覆われていて汗や皮脂がこもりやすい環境だからです。
まず考えられる原因のひとつが「脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)」です。
これは、皮脂の分泌が過剰になり、常在菌のマラセチア菌が増殖して炎症を起こすことで、赤みやかゆみ、そしてかさぶたやフケが出てくるという皮膚の病気です。
たとえば、うちの夫が以前、シャンプー後にフケのような白い粉が出るのを気にして皮膚科を受診したところ、実は脂漏性皮膚炎だったということがありました。
そのとき医師に言われたのが、「頭皮の乾燥ではなく皮脂のバランスの乱れが原因」ということで、本人もびっくりしていました。
次に多いのが「乾燥による皮むけ」です。
冬場など湿度が低い季節には、肌と同じように頭皮も乾燥します。
その結果、表皮のバリア機能が低下して、ちょっとした刺激でも皮膚がはがれやすくなり、かさぶたのようなものができることがあります。
一方で、「シャンプーのすすぎ残し」や「洗浄力の強すぎるシャンプー」などの生活習慣も、頭皮にダメージを与える原因になりえます。
たとえば、「毎日頭をきれいに洗っているつもりなのにフケが出る」と悩んでいた友人は、使っていたシャンプーを見直しただけで、かさぶたの発生がほとんどなくなったそうです。
このように、日常的なケアの中にも、頭皮トラブルの原因は潜んでいるんですね。
また、意外と見落としがちなのが「爪での刺激」です。
無意識に頭をかいたり、痒みがあって爪を立ててしまったりすることで、小さな傷ができ、それがかさぶたに変わってしまうことがあります。
さらに、育児や仕事でストレスがたまっていると、無意識に頭皮を触ってしまうクセが出ることもあります。
これはちょうど「つい頬杖をつくクセ」と似ていて、気づかないうちに刺激を与えてしまっているんです。
ちなみに、私も子どもが小さかったころ、寝不足とストレスが続いていた時期に、後頭部にかさぶたのようなものができているのに気づきました。
最初は「フケかな」と思っていたのですが、実は寝かしつけ中に自分でも気づかず頭を触っていたのが原因でした。
このように、かさぶたができる原因はひとつではなく、皮膚の病気や生活習慣、無意識のクセなど、いくつかの要因が重なって起こっていることが多いのです。
だからこそ、「かさぶたを剥がすことをやめる」だけではなく、「なぜできるのか」という根本の原因を見極めることが大切になります。
では続いて、その“やめたくてもやめられない癖”とどう向き合うか、かさぶたを剥がす癖をやめるための具体的な方法をご紹介いたします。
かさぶたを剥がす癖をやめるための具体的な方法

「わかっているけど、どうしても剥がしてしまう」
そんなふうに感じている方は、とても多いのではないでしょうか。
実は、頭皮のかさぶたを剥がす行為には、無意識のうちにストレスを和らげようとする心理が隠れていることがあります。
たとえば、私のママ友のひとりは、夜子どもが寝たあとにテレビを見ながら、つい頭を触ってしまう癖があるそうです。
「気づいたら爪に白いかさぶたがついてるの…」と、困ったように笑って話してくれました。
このような無意識の癖をやめるには、まず「気づくこと」が第一歩になります。
つまり、意識して行動を観察し、自分がどんなタイミングで頭を触っているかを知ることが大切です。
たとえば、日中の仕事中だけでなく、リラックスしている夜の時間帯やスマホを触っている時など、気づけば手が頭へ行っている…なんてこともあるかもしれません。
そこで効果的なのが、「手の代わりになるものを使う」方法です。
髪を触りたくなったときには、指先を握ってみたり、保冷剤や冷たいタオルを手に持ってみたりすると、手が頭に向かうクセを意識的に断つことができます。
また、頭皮が乾燥してかゆみを感じやすい場合には、「頭皮用の保湿ローション」や「ミストスプレー」を活用するのもおすすめです。
私自身、冬場に頭皮が乾燥してかゆみが出やすくなる時期があるのですが、無印良品のホホバオイルを使ってから、かさぶたができる頻度がぐんと減りました。
しかも、その習慣ができてからは、頭を触りたくなること自体がだんだん減っていったんです。
さらに、癖をやめる上で大切なのが「代替行動を取り入れる」ことです。
たとえば、無意識に頭を触りそうなタイミングに、お茶を飲む、ハンドクリームを塗る、軽くストレッチをするなど、“別の行動”にすり替えていく方法です。
これはちょうど、子どもがおしゃぶりをやめるときに、代わりのおもちゃやタオルを持たせるのと同じような考え方です。
また、癖をやめた自分をしっかり褒めてあげるのも大切です。
たとえば、「今日は1日触らなかったな」と思った日は、好きなお菓子を食べたり、ゆっくり湯船につかったりして、自分に小さなご褒美をあげてみてください。
このような「できた」という小さな成功体験を積み重ねていくことで、自然と頭皮を傷つける行動が減っていきます。
ちなみに、どうしても癖が治らない場合や、頭皮に炎症が繰り返し起きているような場合には、皮膚科で相談するのもひとつの方法です。
医師に相談することで、必要な治療だけでなく、心理的な背景にも寄り添ったアドバイスを受けられることがあります。
なお、クセというのは一朝一夕に直るものではありません。
だからこそ、焦らずに少しずつ、やさしく自分と向き合いながら取り組んでいくことが何より大切なんだと思います。
では次に、そもそも頭皮にかさぶたを作らないために、普段からできる正しいケア方法についてご紹介いたします。
頭皮の健康を保つための正しいケア方法
かさぶたができる原因の多くは、実は日々のケアに潜んでいます。
だからこそ、かさぶたを防ぐためには、頭皮環境を整えることがとても大切です。
たとえば、スキンケアと同じように「頭皮にも保湿が必要」と言われたら、少し意外に思う方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、実際には頭皮も皮膚の一部であり、乾燥や刺激にとても敏感な場所なんです。
まず、毎日のシャンプーの見直しから始めてみましょう。
洗浄力の強いシャンプーを使っていると、必要な皮脂まで落としてしまい、頭皮が乾燥しやすくなります。
その結果、防御反応として皮脂が過剰に分泌され、脂漏性皮膚炎などの原因になることもあります。
たとえば、私の姉は以前、市販のメントール入りシャンプーをずっと使っていたのですが、あるとき頭皮にポツポツと赤みが出るようになり、皮膚科で「刺激が強すぎるかもしれません」と言われたそうです。
その後、アミノ酸系のやさしいシャンプーに変えてからは、赤みもフケもほとんど出なくなったそうです。
では、どのようなケアが「正しい」と言えるのでしょうか。
まずは以下のポイントを意識してみてください。
① 洗う前にしっかりブラッシング
髪のもつれをほどくだけでなく、汚れやホコリを浮かせておくことで、シャンプーの泡立ちや洗浄効果が高まります。
② 指の腹でやさしく洗う
爪を立てて洗うと、頭皮に細かい傷がつきやすくなり、そこから炎症が広がることがあります。
指の腹を使って、マッサージするように洗うのが理想です。
③ すすぎは丁寧に
泡や洗浄成分が頭皮に残ってしまうと、かゆみや赤みの原因になります。
時間に余裕がないときでも、最低でも1分はしっかりすすぐよう心がけましょう。
④ ドライヤーでしっかり乾かす
自然乾燥は頭皮に雑菌が繁殖しやすくなるため、洗ったあとはできるだけ早めに根元からドライヤーで乾かすことが大切です。
また、頭皮の状態が不安定なときには、週に1〜2回ほどのペースで「頭皮用のクレンジングオイル」や「炭酸シャンプー」を取り入れるのも効果的です。
とくに無印良品のホホバオイルなどは、天然由来でやさしく、敏感肌でも使いやすいと口コミでも評判です。
ちなみに、私自身も産後のホルモンバランスの影響で頭皮が荒れていた時期に、ホホバオイルでクレンジングするようにしてから、明らかにかさぶたやフケが減ってきたと感じました。
肌に直接触れるものだからこそ、信頼できるアイテムを使うことも大事ですよね。
なお、ストレスや睡眠不足も頭皮環境を乱す要因になります。
頭皮に違和感があるときは、体全体からのサインである可能性もありますので、無理をせず、ゆったりとした時間を持つことも心がけてみてください。
それでは次に、かさぶたや頭皮の悩みにまつわるよくある疑問や不安にお答えするQ&Aをご紹介いたします。
さらに知っておきたい!頭皮のかさぶたに関するQ&A

ここまでお読みくださった方の中には、「もっと細かいことも知りたいな」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、頭皮のかさぶたについてよくいただくご質問をQ&A形式でご紹介していきます。
Q1. 頭皮にかさぶたがあると美容院で嫌がられますか?
これは多くの方が気にされるところだと思います。
結論から申し上げますと、多少のかさぶたであれば美容師さんは慣れていますし、特に驚かれることはありません。
ただし、かさぶたが大きかったり、赤みや出血がある場合は、カラーやパーマの施術を断られることもあります。
たとえば、私の友人はかさぶたを剥がした直後にカラーを予約していたのですが、美容師さんに「今日は控えた方がよさそうですね」とやんわり断られたそうです。
そのため、施術の前日には頭皮を触らないよう注意し、清潔な状態で行くのが安心です。
Q2. かさぶたがあるときはシャンプーを控えた方がいいの?
これもよくある疑問です。
かさぶたがあるからといって、シャンプーを完全にやめてしまうのはおすすめできません。
なぜなら、頭皮に汚れがたまると雑菌が繁殖し、炎症が悪化してしまうからです。
そのため、優しい洗浄力のシャンプーで、こすらずなでるように洗い、しっかりすすいであげることが大切です。
なお、洗ったあとにドライヤーでしっかり乾かすことも忘れずに行いましょう。
Q3. かさぶたの部分に薬を塗ってもいいですか?
基本的には、自己判断で市販薬を塗るのは避けた方が無難です。
症状の原因が脂漏性皮膚炎やアトピー性皮膚炎などの場合、合わない薬を使うことでかえって悪化することもあるためです。
たとえば、私の母は市販のステロイド系軟膏を自己判断で使ってしまい、しばらく赤みが引かず困っていました。
したがって、気になる場合はやはり皮膚科で医師に診てもらい、適切な治療を受けることが一番安心だと思います。
Q4. かさぶたをはがすのをやめたら、どのくらいで治りますか?
これはかさぶたの大きさや原因によって異なりますが、軽いものであれば1週間程度で自然にはがれ落ちることが多いです。
ただし、繰り返し同じ場所を触っていたり、洗い方に問題があると、何度も同じ箇所にかさぶたができてしまいます。
よって、「はがさない」だけでなく「環境を整える」こともセットで行うと、より早く回復につながります。
Q5. 子どもの頭にもかさぶたができるの?
はい、実はお子さんにも同じような症状が出ることがあります。
とくに乳児湿疹や乾燥、あるいはシャンプーが合っていないことが原因で、かさぶたのような皮むけが見られることもあります。
ちなみに、私の息子も赤ちゃんの頃、頭のてっぺんに黄色っぽいかさぶたができて、最初はすごくびっくりしました。
ですが、医師に相談すると「乳児脂漏性皮膚炎」で、保湿とやさしい洗髪で自然に改善しました。
ですので、小さなお子さんの場合も、まずは皮膚科で診てもらうのが安心です。
では最後に、今回の記事の内容をやさしくまとめながら、かさぶたケアとの向き合い方を一緒に振り返ってまいりましょう。
まとめ
頭皮にできたかさぶた、つい剥がしたくなってしまうことってありますよね。
「気持ちいいからやめられない」
「ストレスが溜まると無意識に触っちゃう」
そんなふうに感じるのは、決してあなただけではありません。
でも、実はその癖が頭皮トラブルを長引かせたり、繰り返したりする原因になってしまっていることもあるんです。
だからこそ、「なんで剥がしたくなるのかな?」と、自分の気持ちやクセに少しずつ気づいてあげることが大切なんだと思います。
かさぶたをつくらないようにするためには、頭皮の乾燥を防いだり、刺激の少ないシャンプーに変えたりと、日々のケアの中でできることがたくさんあります。
それに、どうしても癖がやめられないときは、無理せず皮膚科で相談してみるのもひとつの手です。
私自身も、子どもを育てながら感じるストレスや寝不足で頭皮が荒れた時期がありました。
だからこそ「気づく・向き合う・整える」この3つのステップで、少しずつ自分の頭皮と仲良くなっていけたら素敵だなと思っています。
あなたのペースで、できることから始めてみてくださいね。
“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本
今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
参考記事
・頭皮弱いと感じたら読むべき6つの対策と医師に相談すべき症状とは
・頭皮クレンジング無印って効果ある?失敗しない使い方と選び方
・頭皮かさぶたはがす楽しいは危険?癖の心理と治す方法を完全解説