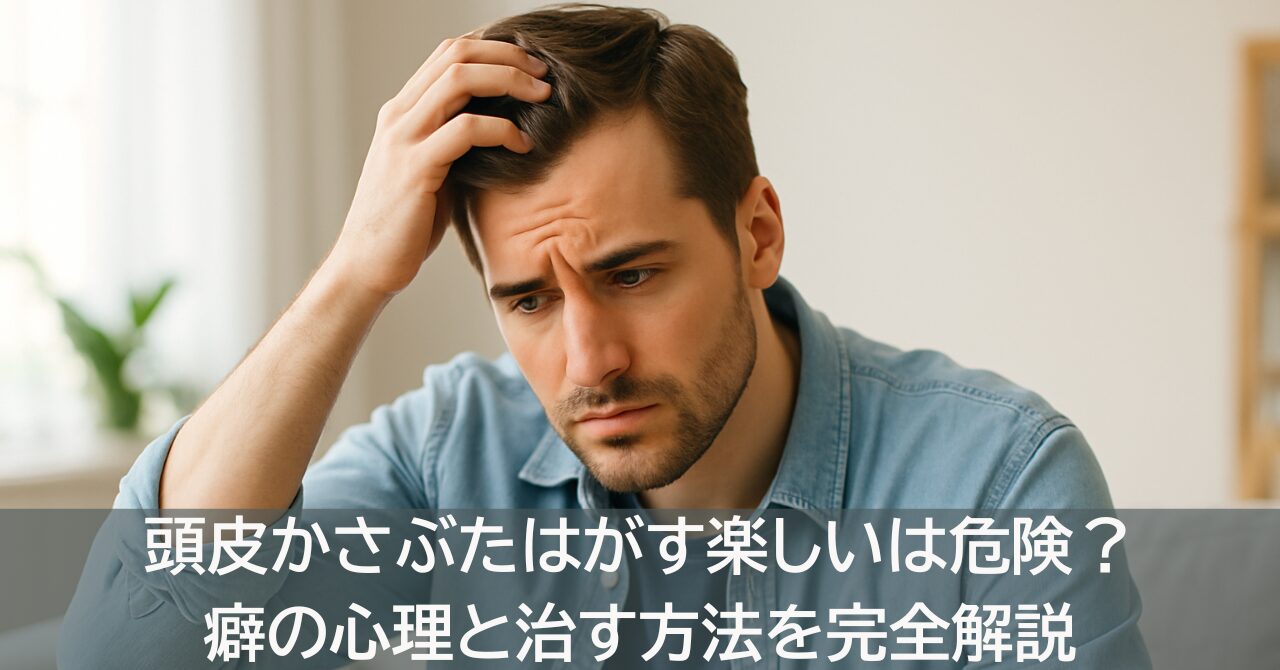頭皮かさぶたはがす楽しい、と感じたことがある方へ。
それって、あなただけじゃないんです。
実は、「頭皮かさぶたはがす楽しい」と感じてしまうのは、ストレスや心理的な癖と深く関係していることがあるんです。
でも、だからといって落ち込んだり、ダメな自分だと思う必要はありません。
この記事では、頭皮トラブルをくり返さないために知っておきたいリスクと、やめたい気持ちに寄り添うケア方法を、やさしく丁寧に解説します。
 頭皮ケア アドバイザーAya
頭皮ケア アドバイザーAya朝の“爆発ヘア”にもう凍りつかない!
毛髪診断士が選んだ8種の有効成分をナノカプセルで毛根まで直届け。
1日1回のモアグロースアップ習慣で、ハリ・コシ・ツヤのある髪へ。
(心の声:この髪なら、もう人前でも堂々とできる)
男女兼用の薬用育毛剤。
今なら 4,400円 → 3,366円/送料無料・縛りなしで安心デビュー
▶ 詳しく見る
- 「かさぶたをはがすのが楽しい」と感じる心理背景を徹底解説
- 無意識に続けてしまう人の特徴とストレスとの関連性を紹介
- 炎症・薄毛・色素沈着などのリスクを医師監修でわかりやすく解説
- やめたい人のための具体的な対策法とおすすめアイテムを紹介
頭皮のかさぶたをはがすのが楽しいと感じる心理とは?
実は「頭皮のかさぶたをはがすのが楽しい」と感じる方は、意外と少なくありません。
けれども、その行動には自分でも理由がよくわからない、やめたいけどやめられない…そんな葛藤を抱えている方が多いのではないでしょうか。
この「楽しい」という感覚の裏側には、いくつかの心理的なメカニズムが関係していると考えられています。
まず、かさぶたをはがすときに感じる“スッとした解放感”や“達成感”は、脳内で快感物質であるドーパミンが分泌されているからと言われています。
たとえば、毛穴の詰まりを取るシートをはがしたときや、角栓が取れたときのスッキリ感と似た感覚ですね。
また、ストレスや緊張が続いているとき、人は無意識に「安心できる習慣」や「手元の刺激」を求める傾向があります。
このような状態では、頭を無意識に触ってしまったり、髪をいじったり、かさぶたをはがす行為が“癖”として定着しやすくなるのです。
さらに、皮膚をいじる行動は「皮膚むしり症(スキンピッキング症)」と呼ばれる軽度の精神的習慣や依存傾向とも関連があるとされています。
ただし、だからといって深刻に悩みすぎる必要はありません。
誰にでも、爪を噛む、ペンを回す、髪を触るなど、無意識のクセはあるものです。
それが「たまたま頭皮のかさぶたをはがすことだった」というだけで、自分を責める必要はないんですよ。
とはいえ、頭皮は髪の毛を守る大切な皮膚ですので、無意識のうちに何度も傷つけてしまうと、将来的に炎症や薄毛の原因になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
実際、「気づいたら血が出ていた」「治ってはまた触ってしまうの繰り返し」というお声もよく耳にします。
ちなみに、私も昔、頭皮の乾燥がひどかった時期に、シャンプー後の乾いたかさぶたがポロポロ取れるのが妙に気持ちよく感じてしまったことがありました。
最初は悪気があったわけではないのですが、気づいたら無意識に触ってしまうようになっていて、「なんでやっちゃうんだろう」と自己嫌悪になったこともあります。
でも、原因を知ったり、頭皮ケアを見直すことで、自然とその習慣から離れることができました。
したがって、まずは「楽しい」と感じる心理を知ることが、やめたいときの第一歩になります。
それでは次に、はがすのをやめられない人に共通する特徴や、ストレスとの関係について詳しく見ていきましょう。
“毛髪診断士監修『モアグロースアップ』。8種の有効成分をナノカプセルで毛根まで直浸透キャンペーン実施中!
今なら公式サイトで。今なら4,400円→3,366円送料無料・縛り期間なしで安心スタート
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
はがすのをやめられない人の特徴とストレスとの関係

頭皮のかさぶたを「ついつい」さわってしまう方には、いくつかの共通する特徴があります。
たとえば、仕事や子育てなどで日常的にストレスを感じていたり、完璧主義で「ちゃんと治っているか気になる」とつい触ってしまうような方も少なくありません。
というのは、かさぶたをいじる行為は、無意識のうちに心の中の不安や緊張を紛らわせる“ストレス発散の手段”になっていることが多いからです。
たとえば、テレビを見ながら無意識に頭を触ってしまったり、寝る前に布団の中で「ここ、まだかさぶたあるな」と確認してしまったり。
それが習慣化してしまうと、脳が「触ることで落ち着く」と覚えてしまい、やめようとしてもまた手が伸びてしまう…そんな状態に陥りやすいのです。
しかも、現代の生活ではスマホやパソコンを長時間使うことで目も脳も疲れがちです。
すると、知らず知らずのうちに“指を動かして気分を落ち着かせる行動”をとる方が増える傾向があります。
つまり、頭皮のかさぶたをはがす行為は「自分を落ち着かせるための無意識の儀式」のようなものになっているとも言えるんですね。
また、几帳面で「中途半端が嫌い」という性格の方も、治りかけのかさぶたを「中途半端に残っているのが気になる」と感じてしまうことがあります。
そういう方は、気づいたら指でなぞって「あとちょっとだから取っちゃおう」と、無意識に行動してしまうことがあるんです。
私の友人にも、普段はとても穏やかで優しいママがいるのですが、忙しい時期になると「気づいたら頭触ってた」とよく話してくれます。
しかも、髪の毛の分け目にできた小さなかさぶたを毎日少しずつはがしてしまい、結局治るまでに何週間もかかってしまったこともあるそうです。
とはいえ、それを責めたり否定する必要はまったくありません。
なぜなら、これは特別な人だけに起こる現象ではなく、多くの人が「やめたいのにやめられない」と感じながら日々を過ごしているからです。
更には、ストレスが強くなりすぎると、頭皮だけでなく爪や唇、手のひらなどをいじる“皮膚むしり”の傾向が出てくることもあります。
これらは「スキンピッキング症」という名前もついているほど、専門的にも注目されている心の反応の一つです。
なお、こうした傾向が強くなる背景には、ホルモンバランスの乱れや睡眠不足、自律神経の不調も関わっていることがあります。
だからこそ、ただ「やめよう」と思うだけではなく、生活の中で少しずつ心と体のバランスを整えていくことも大切なんです。
それでは次に、こうした癖をやめたいときに役立つ具体的な対策法や、毎日のちょっとした工夫についてご紹介いたします。
頭皮のかさぶたをはがすリスク|炎症・薄毛・色素沈着の可能性
頭皮のかさぶたをはがす行為は、一見すると小さなクセのように思えるかもしれません。
しかしながら、実はその行為が続くことで、思わぬ肌トラブルや髪の悩みに発展してしまうリスクがあるんです。
まず大きなリスクとして挙げられるのは、「炎症の慢性化」です。
かさぶたは、傷ついた皮膚が自然に修復しようとする過程でできる“天然の絆創膏”のようなものです。
それを無理にはがしてしまうと、まだ治りきっていない皮膚が再びむき出しになり、菌が入りやすい状態になってしまいます。
そのため、繰り返し触ることで傷が深くなり、炎症が長引く原因になることがあります。
たとえば、小さなひっかき傷だったものが、何日たっても赤みやかゆみが治まらず、じゅくじゅくした状態になってしまったというご相談はよくあります。
更には、頭皮という場所は髪の毛が密集しているため、湿度が高く蒸れやすく、雑菌が繁殖しやすい環境です。
よって、一度炎症が起こると、なかなか自然治癒しにくく、何度も悪化と回復を繰り返すことになりかねません。
そして、もう一つの深刻なリスクは「薄毛の原因になること」です。
なぜなら、頭皮が傷ついて炎症を起こすと、髪の毛を生み出す毛根の細胞にもダメージが及ぶことがあるからです。
毛根が慢性的にダメージを受けると、新しい髪の毛が生えにくくなり、生えても細くて弱い毛になってしまうことがあります。
私の知人で、長年かさぶたをはがすクセがあった女性がいるのですが、いつの間にかその部分だけ髪の密度が減ってしまい、慌てて皮膚科を受診したそうです。
医師には「頭皮の繰り返しの刺激で毛乳頭が弱ってしまった可能性がある」と言われ、非常にショックを受けていました。
また、意外と見落としがちなのが「色素沈着」の問題です。
というのは、傷を繰り返すことで皮膚がメラニンを生成しやすくなり、結果としてその部分だけ黒ずんで見えてしまうことがあるからです。
すなわち、将来的に頭皮の一部に茶色い跡が残ってしまう可能性もあるということです。
頭皮は髪に隠れているとはいえ、美容室などで人に見られる機会もありますし、自分自身でも鏡で見たときに気になってしまうこともありますよね。
ちなみに、ヘアカラーをするときも、頭皮に小さな傷があると薬剤がしみてしまい、痛みを感じたり炎症を悪化させる要因になってしまうことがあります。
したがって、かさぶたをはがす行為は、単なる癖というよりも、肌や髪の健康に影響を与える“積み重ね”として捉えておくことが大切です。
では次に、こうしたトラブルを防ぎつつ、自然にやめていくための対策法や生活の中でのちょっとした工夫についてご紹介してまいります。
ついやってしまう人におすすめの対策法と習慣改善アイデア

頭皮のかさぶたをはがすのをやめたいと思っていても、無意識のうちに手が伸びてしまう…そんな経験、実は多くの方に共通しています。
だからこそ、ただ「やめよう」と我慢するのではなく、自然に行動を変えていける対策や工夫を取り入れることが大切なんです。
まずおすすめしたいのが、「手を使う行動を別のことに置き換える」ことです。
たとえば、無意識に頭を触ってしまうタイミングに、ストレッチや指先マッサージをするようにすると、手を動かしたい衝動を和らげることができます。
また、子育て中の方なら、子どもと折り紙をしたり一緒にお絵かきをするだけでも、手の動きが意識的になってかさぶたを触る時間が自然と減ってくることもあります。
更には、爪を短く整えるのも効果的です。
というのは、爪が長いとどうしてもひっかきやすく、無意識のうちに頭皮を傷つけてしまうリスクが高まるからです。
逆に、こまめに爪を短く切っておくと、はがしにくくなり、行動そのものを予防しやすくなります。
加えて、頭皮に触れにくい状況を作るのも一つの方法です。
たとえば、夜寝るときに綿の手袋をつけてみたり、家にいる時間はヘアバンドや帽子をかぶって頭をカバーしておくのもおすすめです。
私の知人は、家事をしている間につい頭を触ってしまうことが多かったそうなのですが、髪をしっかりまとめてバンダナで覆うようにしたところ、触れる回数が大きく減ったと話してくれました。
また、「治っていく過程が目で見てわかるように記録する」というのも意外と効果があります。
たとえば、頭皮の写真を数日おきに撮って、スマホのメモアプリに「今日は触らずに過ごせた」など簡単なコメントを添えるだけでも、継続する意識が高まります。
すると、「あ、昨日頑張れたんだ」と自信にもつながり、行動が前向きになっていきます。
ちなみに、どうしても触ってしまうという方には、気分転換を意識的に取り入れるのも大切です。
なぜなら、ストレスや疲れがたまると無意識の行動が出やすくなるため、ちょっとしたリラックスタイムをつくるだけでも、行動の頻度がぐっと減ることがあるからです。
お気に入りの音楽を聴いたり、好きな香りのアロマをたいたり、ほんの10分お茶をゆっくり飲む時間をとるだけでも、心の余裕が少しずつ戻ってきますよね。
尚、誰かと一緒にこの習慣改善に取り組むのも励みになります。
たとえば、ご家族に「私、最近頭を触っちゃうクセがあるから、もし見かけたらやさしく声かけてくれる?」と頼んでおくと、自分では気づけないタイミングでブレーキをかけることができます。
このように、少しずつ自分の行動を観察しながら、無理なく取り組める習慣を増やしていくことで、自然と「触らない日」が増えていきます。
それでは次に、医師の視点から見た頭皮ケアの方法や、かさぶたができにくい頭皮環境を整えるためのアイテムについて詳しくご紹介いたします。
医師がすすめる!頭皮を健康に保つケア方法とアイテム
頭皮にかさぶたができやすい方や、繰り返しトラブルを感じやすい方にとって、「健康な頭皮環境を整えること」はとても重要なポイントです。
とはいえ、ただシャンプーを丁寧にするだけでは根本的な改善にはつながらないことも多いんですね。
そこで今回は、皮膚科の医師や頭皮ケアの専門家がすすめる実践的な方法と、おすすめのアイテムについてご紹介いたします。
まずは基本となるのが、「洗いすぎず、汚れをきちんと落とす」シャンプー習慣です。
というのは、頭皮が乾燥してかさぶたができてしまう方の多くが、洗浄力の強いシャンプーを毎日使い続けていたり、1日に何度も洗っていたりするケースが少なくないからです。
実際、ある皮膚科の先生は「強すぎる洗浄力は、頭皮のバリア機能を壊しやすいので、アミノ酸系など低刺激のものを選びましょう」とお話しされていました。
たとえば「コラージュフルフル」や「ミノン薬用シャンプー」などは、敏感肌の方やかゆみ・かさぶたが気になる方にも比較的安心して使えるアイテムとしてよく紹介されています。
また、シャンプーのあとは「しっかりすすぐこと」も大切です。
なぜなら、洗い残したシャンプーやトリートメント成分が頭皮に残ってしまうと、毛穴が詰まり、炎症やかさぶたの原因になることがあるからです。
特に、耳のうしろや生え際などは泡が残りやすい部分ですので、意識して丁寧に流すようにしましょう。
更には、シャンプー後の頭皮の保湿もおすすめです。
意外と知られていないのですが、顔に化粧水や乳液をつけるのと同じように、頭皮にも保湿が必要なんですね。
「乾燥=皮脂が足りない」と思われがちですが、実は乾燥が進むと皮脂が過剰に分泌され、それがかさぶたやかゆみの原因になることもあります。
市販の頭皮用ローションや保湿スプレーには、ヒアルロン酸やグリチルリチン酸など、炎症を和らげる成分が入っているものもあり、日々のケアに取り入れるだけでずいぶん変わってきます。
たとえば、私のママ友は産後にホルモンバランスが乱れて頭皮トラブルが増えたのですが、皮膚科で勧められた保湿ローションを使い始めてから、かゆみが落ち着いて触る回数も減ったと話してくれました。
また、生活習慣も頭皮環境に大きく影響します。
すなわち、睡眠不足や偏った食事、運動不足などが続くと、自律神経やホルモンのバランスが崩れ、皮膚の回復力も弱まってしまうのです。
よって、頭皮のケアは外側だけでなく、内側からのケアも意識してあげることがとても大切なんですね。
ちなみに、ドライヤーを使うときも熱風を1点に当てすぎると乾燥やダメージの原因になるため、温風と冷風を使い分けたり、少し距離を離して風を当てるだけでも、頭皮への負担が減らせます。
では最後に、すでにかさぶたをはがしてしまった後の対処法や、炎症を起こしてしまったときにどう対応すればよいのか、次で詳しくお伝えいたします。
それでも気になる…はがした後の正しい処置と治す方法

どれだけ気をつけていても、ふとした瞬間にかさぶたをはがしてしまうことってありますよね。
特に、気づいたら指が動いていたり、なんとなく違和感があって触ってしまった…という方も少なくないと思います。
しかしながら、大切なのは「やってしまった後に、どうケアするか」です。
まず、はがしてしまった部分が赤くなっていたり、血がにじんでいた場合は、清潔に保つことが最優先です。
というのは、頭皮は皮脂腺が多く、細菌が繁殖しやすい場所なので、そのまま放置してしまうと炎症が広がってしまうこともあるからです。
たとえば、私の知人はうっかりかさぶたを爪ではがしてしまい、そこから数日後にかゆみが増して皮膚科に駆け込んだことがありました。
診察では「二次感染の兆候がありますね」と言われ、抗菌軟膏を処方されたそうです。
そこでまずおすすめしたいのは、洗浄力が穏やかで頭皮にも使える殺菌効果のある洗浄剤で、やさしく洗い流すことです。
具体的には、赤ちゃん用や敏感肌用の無添加シャンプーなどが安心です。
しっかり洗って、すすいだ後は、できるだけ自然乾燥ではなくドライヤーで乾かすようにしましょう。
というのも、濡れたままだと雑菌が繁殖しやすく、再びかさぶたになったり、湿疹の原因になってしまうことがあるからです。
乾かした後には、炎症を抑える成分が入った頭皮用ローションや、皮膚科で処方された軟膏を塗るのが効果的です。
市販品であれば、グリチルリチン酸やアラントインなどが含まれたローションを選ぶと、かゆみや炎症を抑える手助けになります。
ただし、ジュクジュクしていたり、強い痛みがある場合は、自己判断せずに皮膚科を受診されることをおすすめします。
なぜなら、軽い炎症に見えても、毛穴の奥で炎症が進んでいたり、毛包炎などの症状に発展しているケースもあるからです。
尚、病院を受診するのが不安な方もいらっしゃると思いますが、頭皮のトラブルは早めの対処が治りを早くするポイントになります。
そして、再び同じ場所を触らないためにも、ワセリンなどで軽く覆っておくのも一つの方法です。
すなわち、肌を保護しつつ、摩擦や外部からの刺激を防ぐことで、自然治癒力を引き出すことができます。
ちなみに、お風呂あがりなどに化粧水や乳液をつける習慣がある方は、ついでに頭皮もケアする「ながら保湿」を取り入れると、継続しやすくなります。
また、同じ場所ばかりにかさぶたができてしまう方は、分け目を変える、ヘアスタイルをゆるめにするなど、頭皮への物理的な負担を軽減する工夫もおすすめです。
頭皮は髪を育てる「畑」のような存在ですから、土壌(地肌)が元気でないと、きれいな髪も育ちにくくなってしまうのです。
それでは最後に、今回の内容をふまえて、記事全体のまとめと読者の皆さまへのメッセージをお届けいたします。
まとめ
ついついやってしまう「頭皮のかさぶたをはがす」行為ですが、理由がわからずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
私自身も、気づいたら触ってしまっていたことがあり、「なんでやっちゃうんだろう…」と後悔する日もありました。
でも、そういった癖にはちゃんと理由があって、ストレスや気分の落ち込み、皮膚の不快感などが関係していることがあるんです。
とはいえ、ずっと続けていると炎症が悪化してしまったり、髪が抜けてしまったりすることもあるので、できるだけ早くケアを見直してあげることが大切なんですね。
無理にやめようと頑張るよりも、まずは「なぜ触ってしまうのか?」をやさしく見つめてあげて、少しずつ新しい習慣に置きかえていくことがとても効果的だと感じました。
また、医師のアドバイスを取り入れた頭皮ケアや、市販のアイテムもとても心強い味方になります。
私たちは、毎日の中でつい頑張りすぎてしまうこともありますが、まずは「触らずにすごせた日」を自分で褒めてあげながら、少しずつ健やかな頭皮に近づいていけたら素敵ですね。
“毛髪診断士監修『モアグロースアップ』。8種の有効成分をナノカプセルで毛根まで直浸透キャンペーン実施中!
今なら公式サイトで。今なら4,400円→3,366円送料無料・縛り期間なしで安心スタート
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
参考記事