「はげ 百人一首」と聞いて、少し笑ってしまった方もいるかもしれません。
でも実はこの語呂合わせ、「うかりける~」という切ない恋の和歌を覚えるための工夫なんです。
60代男性髪型薄毛対策に似て、ちょっとしたきっかけが自信につながることってありますよね。
このコラムでは、60代男性髪型薄毛対策のように、百人一首をもっと身近に、もっと楽しく覚えられる方法をご紹介します。
古典にふれるきっかけとして、今こそ「うっかりハゲ」の奥深さをのぞいてみませんか。
 Aya
Aya「“最近疲れてる?”って言われたその理由、頭皮だったかも。」
(心の声:髪があるだけで、こんなに若く見えるなんてズルい…)
男女兼用の本気の育毛剤
今なら13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー
→ 詳しく見る
- 第74番「うかりける~」の和歌を「うっかりハゲ」という語呂合わせで覚える方法を紹介
- 和歌の意味と背景、作者の恋心をわかりやすく解説
- 決まり字や競技かるたに役立つ記憶法や具体例を豊富に紹介
- 家庭で楽しめる百人一首学習アプリや語呂合わせ一覧も充実紹介
「うっかりハゲ」って何?百人一首第74番の語呂合わせ解説
「うっかりハゲ」という言葉を初めて耳にした方は、少し驚かれるかもしれませんね。ですが、これは百人一首に出てくる第74番の和歌を覚えるためのユニークな語呂合わせのことなんです。
百人一首の第74番は、源俊頼朝臣(みなもとのとしよりあそん)が詠んだ和歌です。
「うかりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを」
この歌を覚える際に「うっかりハゲ」という言葉を使うと、最初の決まり字(う・か・り)と、印象的な語(はげ)を自然に連想できるため、記憶に残りやすくなるんです。
では、なぜ「うっかりハゲ」というフレーズが百人一首で使われるようになったのでしょうか?その理由は、競技かるたにあります。
競技かるたでは、いかに早く和歌の「決まり字」を聞き取って札を取るかが勝負です。この第74番は「うかりける」が冒頭に来るため、少しでも早く反応するには語呂合わせで覚えておくと便利なんです。
たとえば、学生時代に百人一首大会に出場した方なら、「うっかりハゲ」という言葉を口にしただけで、すぐにこの歌が思い出せた、という経験があるかもしれません。
「うかりける」は、「つれない」「冷たい」という意味の古語「うかる」から来ています。そして「はげし」は、激しい風や感情の動きを表現しています。
つまり、この歌は「冷たくあしらわれたあの人に、初瀬山から吹き下ろす山おろしの風のような激しさであれと祈ったわけではないのに……」という、切ない恋心を詠んでいるんですね。
ここで「初瀬(はつせ)」という地名が登場します。日本では古くから、初瀬観音(長谷寺)が縁結びや恋愛成就の祈願で知られており、この和歌にもそうした背景がにじんでいます。
また、「山おろし」という自然現象が心の揺れと重なることで、感情の激しさがリアルに伝わってきます。たとえば、台風の前日に窓がガタガタ鳴るような風が吹いてきて、「ああ、私の気持ちもこんなふうにざわついてるなぁ」と感じたことはありませんか?
このように、語呂合わせの「うっかりハゲ」はただの覚え方ではなく、歌の内容や情景、感情の動きまでイメージとして結びつけてくれる大切なツールなんです。
ちなみに、百人一首のなかにはこのように語呂合わせで覚えやすい歌が他にもいくつかあります。たとえば「ありあけの つれなく見えし 別れより」なども「ありつれ別れ」という語呂で覚えることがあります。
このような覚え方を知っておくと、かるたの大会での勝率もぐっと上がりますし、何より和歌の世界がぐっと身近に感じられるようになりますよ。
それでは次に、この和歌を詠んだ源俊頼朝臣がどのような人物だったのか、そしてどのような恋の背景があったのかを深掘りしてみましょう。
“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本
今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
和歌の意味を深掘り:源俊頼朝臣の恋心と初瀬観音
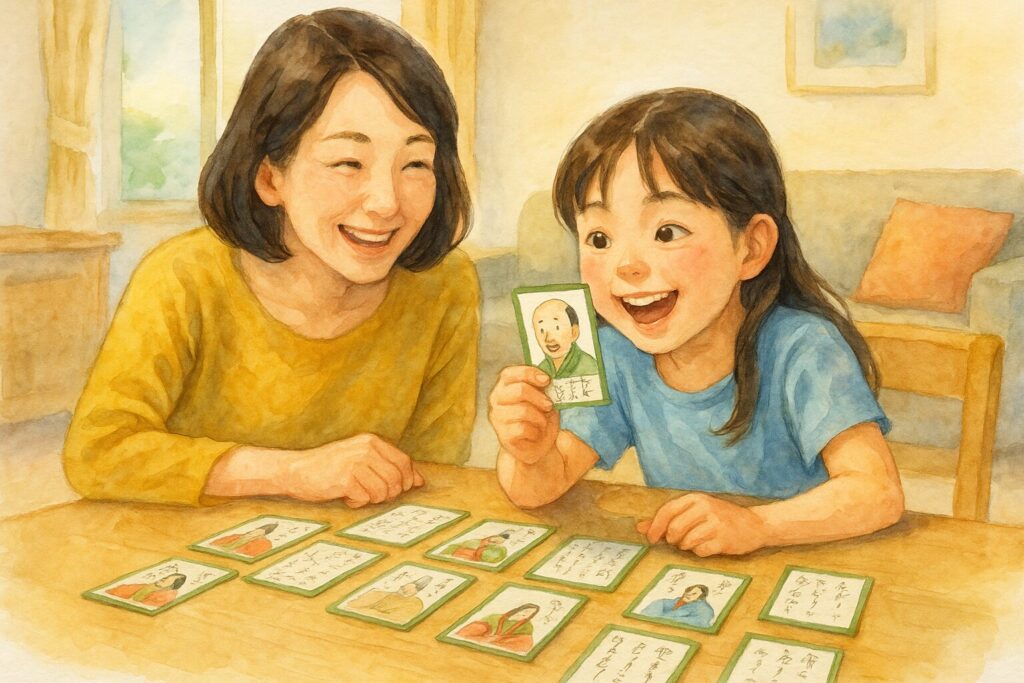
百人一首第74番の和歌を詠んだのは、源俊頼朝臣(みなもとのとしよりあそん)という平安時代の歌人です。
この方は、藤原俊成や藤原定家といった後の大歌人たちにも大きな影響を与えた人物で、『金葉和歌集』の撰者でもあります。
さて、この和歌の意味をもう一度、やさしくかみ砕いてみましょう。
「うかりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを」
現代語にすると、「つれない人の心が、初瀬山から吹きおろす風のように激しくなれ、なんて祈った覚えはないのに…」というニュアンスです。
つまり、好きな人からそっけなくされて傷ついてしまい、その想いがどうしようもないほどにあふれている状態を詠んでいるんですね。
この気持ち、今の時代でも十分に共感できます。
たとえば、SNSでずっと連絡を取り合っていた人が、ある日突然そっけない返信しかしなくなったとします。
理由もわからず、ついスマホを何度も見返して、「何か私、悪いこと言ったかな…」と落ち込んでしまう。そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。
その心のざわつきが、まるで「山おろし」の風のように冷たく吹きつけてくる。
この歌は、まさにそんな気持ちを千年前に詠みあげたものなのです。
ところで「初瀬」とは、奈良県桜井市にある「長谷寺(はせでら)」のある場所のことです。
ここは古くから「恋愛成就」や「縁結び」の祈願所として知られていて、平安の昔から多くの人々が参詣してきました。
俊頼も、おそらくこの初瀬観音に恋の成就を祈るために訪れたのでしょう。
その道中や帰り道、風が激しく吹きつけてくる中、ふと浮かんできたのがこの切ない和歌だったのかもしれません。
たとえば、子育て中のママさんが、日々の忙しさのなかでふと過去の恋愛を思い出す瞬間があるように、俊頼も現実と理想のはざまで心を揺らしていたのかもしれませんね。
しかも、「祈らぬものを」と結んでいるところに、強い感情の裏返しを感じます。
本当はそう願っていたのかもしれないけど、あえて「祈ってないのに…」と言うことで、未練や諦めを隠そうとしているようにも読み取れます。
ちなみに、俊頼は恋の歌だけでなく、社会や自然に対する感受性の高い和歌も多く残しており、感情の陰影を細やかに描く力に長けていた歌人でした。
だからこそ、この和歌にも一筋縄ではいかない複雑な気持ちが込められていて、読む人の心にじんわりと響くのかもしれません。
更には、「山おろし」や「初瀬」といった日本独自の自然や地名が登場することで、和歌の世界観がとても豊かに広がっているのも特徴です。
それは、まるで季節の風景と自分の心情がぴったり重なっているような不思議な感覚を覚える一首でもあるのです。
このように、たった31文字の短い詩の中に、風景・人物・感情が緻密に織り込まれているのが、百人一首の魅力でもあります。
次に、その百人一首を実際の「競技かるた」でどのように活かしていけるのか、覚え方やポイントをお伝えしていきますね。
決まり字を覚えるコツ:競技かるたでの活用法
百人一首を遊びとして楽しむだけでなく、競技かるたとして本格的に取り組む人にとって、「決まり字」をいかに早く正確に覚えるかは非常に重要なポイントです。
「決まり字」とは、上の句を読まれたときに、それに対応する下の句が唯一になるような音の数のことを指します。
たとえば、さきほどの第74番「うかりける 人を初瀬の 山おろしよ~」は「う」から始まる歌ですが、「う」で始まる歌はほかにもいくつかあるため、「うかりける」の「か」くらいまで聞かないと札を正確に取ることはできません。
こうした場合、たとえば「うっかりハゲ」という語呂合わせを使うと、音とビジュアルで記憶が結びつくため、試合中にパッと反応できるようになるんですね。
これはちょうど、子どもの名前を呼ぼうとして一瞬「あれ、なんだっけ」となるときに、リズムや口ぐせで思い出すような感覚と似ています。
競技かるたの大会では、音の瞬発力と記憶の精度がそのまま勝敗に直結します。
だから、選手たちは「決まり字」を暗記するだけでなく、語呂合わせ・歌の意味・情景をセットで覚えておくことが多いです。
たとえば、「ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川~」のようなインパクトのある歌は、色や風景のイメージと一緒に記憶されるため、聞いた瞬間に脳がスイッチオンのような状態になります。
私の場合は、「うかりける~」の札を覚えるとき、「初瀬の山から突風が吹いて、髪がばさっとなびくようなイメージ」で覚えました。
それと同時に、子どもに「帽子ちゃんとかぶりなさい」と言った翌日に限って、風が強くて、結局本人が飛ばされた帽子を追いかけるという笑える一コマを思い出すんです。
このように、風・髪・うっかり・はげしい、というキーワードが連動すると、競技の場面でもすっと札が浮かんできます。
つまり、決まり字の暗記は、単なる反復練習だけではなく、物語やイメージと組み合わせることで、ぐっと覚えやすくなるんですね。
ちなみに、最近では「競技かるた」専用のトレーニングアプリや、フラッシュカード形式の教材も人気です。
特に小学生のうちから始めると、耳と目の連携が早く身につくので、「うかりける」のような3文字決まりでも、すぐに判断できるようになる子もいます。
また、百人一首を家族で楽しむ場面も増えていて、親子で語呂合わせを考えたり、独自の記憶法をシェアし合うのも学びのひとつです。
更には、札を取る瞬間の「ぴしっ」とした音や、読まれる声のリズムが心地よく、集中力を高める習慣にもつながっているようです。
このように、決まり字の記憶法には個人差がありますが、語呂合わせや感情にひもづいた覚え方は、誰にとっても効果的な手段のひとつだといえるでしょう。
では次に、百人一首に数多く詠まれている「恋の歌」のなかで、この第74番がどんな特徴を持っているのかを、他の歌と比べながら見ていきましょう。
百人一首の恋の歌:他の恋歌との比較と特徴
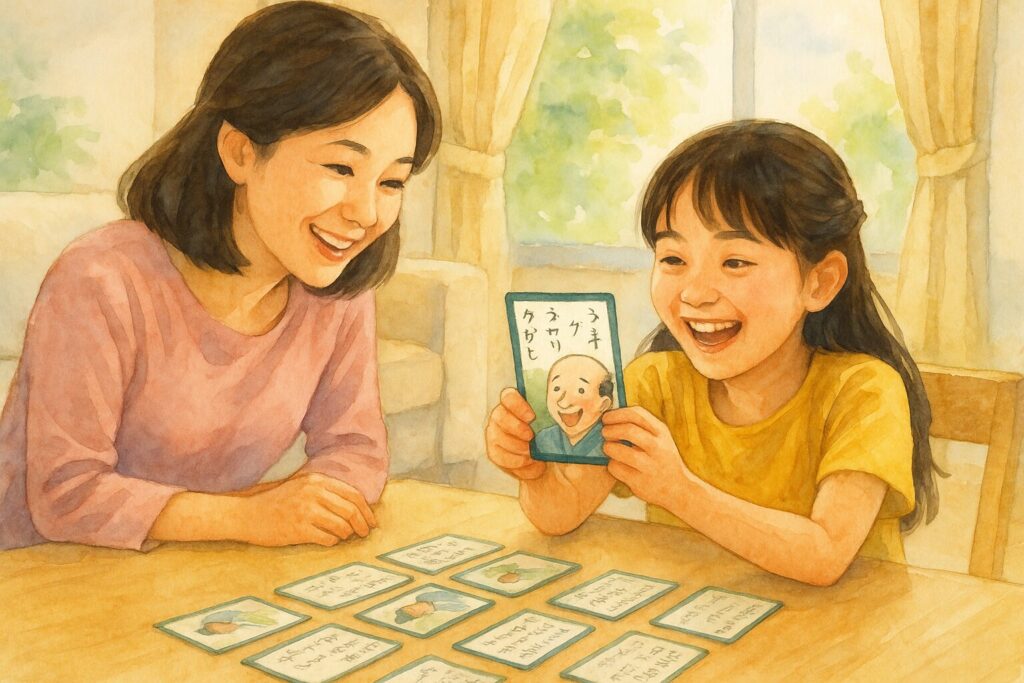
百人一首には、さまざまな恋のかたちが詠まれています。
その中でも、第74番「うかりける 人を初瀬の 山おろしよ~」は、相手に思いが届かず、切なくなってしまう“報われない恋”の心情を表した一首です。
このような恋の歌は、現代で言えば「片思いあるある」のような感情とも重なりますよね。
たとえば、LINEの返信が遅かったり、既読スルーされたときに、「もしかして冷められたのかな…」と心がモヤモヤした経験はありませんか。
この歌のように、「そんな冷たい態度になってほしいなんて祈ったわけじゃないのに」と、やり場のない気持ちに揺れる姿は、今も昔も変わらないのだなあと感じます。
一方で、百人一首には甘く優しい恋の歌もたくさん収められています。
たとえば、第18番の藤原敏行朝臣の
「住の江の 岸による波 よるさへや 夢のかよひ路 人目よくらむ」
この歌は、「夢の中でさえ、あなたに会いに行くのをためらってしまうのは、人目が気になるからでしょうか」という、なんとも奥ゆかしい恋心を詠んだ一首です。
比べてみると、俊頼の歌は感情の高ぶりが風にたとえられていて、とてもストレートな表現なのに対し、敏行の歌は繊細で、じんわりと心に染みてくるような印象ですね。
また、よく知られている第40番の平兼盛の歌
「忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで」
では、恋心を隠していたつもりなのに、表情や仕草にあふれてしまって、周囲に気づかれてしまった…という、こちらも現代に通じる“好きバレ”のような情景が描かれています。
いわば、俊頼の歌が「こじれた恋」、敏行の歌が「叶わぬ恋」、兼盛の歌が「隠せない恋」と、それぞれ異なる恋の角度を映しているように感じられます。
ちなみに、百人一首に登場する恋の歌は全体の約4割を占めるとも言われていて、いかに当時の人々が恋という感情に敏感だったかがうかがえます。
更には、身分制度や結婚のあり方が今とは大きく異なっていた平安時代では、恋愛は「人目を忍ぶもの」「想いを秘めるもの」という前提がありました。
だからこそ、歌の表現にも遠回しな比喩や自然にたとえる技法が多く使われているのです。
たとえば、「山おろしの風」に心を託す俊頼のように、直接は言えない気持ちを風景に重ねることで、相手に伝えようとする工夫が見られます。
こうした点は、現代でもSNSの投稿や日記などで「空がきれいで泣きそうになった」と感情を隠すように吐露する姿と、どこか似ていると思いませんか。
また、歌によっては恋の始まりを描いたものもあり、第41番「恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか」では、「誰にも言ってないはずなのに、噂だけ先に広がってしまった」と、恋の戸惑いが素直に表現されています。
このように、百人一首の恋の歌には、現代の私たちが感じる恋愛の喜びや切なさが、千年以上も前から変わらず詠まれていることがわかります。
では、こうした和歌の世界をもっと身近に楽しむにはどうしたら良いのでしょうか。
次は、百人一首をより楽しく学べるおすすめのアプリやツールについてご紹介していきますね。
関連アプリで楽しく学ぶ:おすすめの百人一首学習ツール
百人一首というと、少しかしこまったイメージを持つ方も多いかもしれません。
けれど、最近ではスマホアプリやデジタル教材を活用することで、もっと手軽に、もっと楽しく学べるようになってきました。
特に、お子さんがいるご家庭では、ちょっとした空き時間や移動中にも遊び感覚で和歌に触れられるので、育児中のママさんにもぴったりの方法です。
まず代表的なのは、『小倉百人一首 かなつみ』というアプリです。
このアプリは、札取りゲームを通じて「決まり字」を自然に覚えられる構成になっていて、視覚と聴覚の両方から記憶をサポートしてくれます。
たとえば、お子さんと一緒に競争して遊ぶように使えば、学習というより“百人一首ごっこ”のような感覚になり、覚えることへの抵抗が少なくなるのではないでしょうか。
また、和歌がランダムに読まれる「読み上げ機能」付きのアプリも増えてきており、耳で覚えるタイプのお子さんや親御さんにとって非常に助かります。
たとえば、朝の支度中にアプリで読み上げを流しておくだけでも、耳が自然とリズムを覚えてくれることがあります。
これは、童謡を覚えたときと同じような効果で、音に慣れることが暗記の第一歩になるのです。
ちなみに、大人向けには『百人一首クイズ』のような知識を深めるアプリもあります。
和歌の意味や作者のプロフィールが解説されていて、「この歌って恋の歌だったんだ」といった新たな発見ができるのも楽しいポイントです。
更には、「百人一首かるた読み上げ機」アプリのように、実際のかるた大会を模して札を読むだけに特化したアプリもあり、競技かるたに興味がある方にもおすすめです。
自宅で練習するには十分な機能がそろっていて、お子さんが大会に出たいと言い出したときの練習にも役立つでしょう。
尚、紙のカードとアプリを併用する方法もおすすめです。
たとえば、手作りの百人一首カードを使いながら、アプリで読み上げを流すことで、視覚と聴覚、さらには手の動きも含めた「全身で覚える」体験になります。
これは、ダンスの振り付けを覚えるときに、見て、聞いて、動いて、といった複数の感覚を使うのと同じような学習効果があります。
私の知り合いのママさんも、子どもが小学校で百人一首の大会に出ると聞き、家族でアプリを使って練習を始めたそうです。
最初は札も読めず、「これ、なんて読むの?」と戸惑っていたお子さんも、1週間後にはスラスラと暗唱していたそうで、アプリの力に感動していました。
このように、百人一首の学び方も時代とともに進化しています。
和歌を通じて古典の世界に触れつつ、親子での時間や学習効果も得られるとなれば、ちょっと試してみたくなりませんか。
では最後に、他にも知っておくと役立つ、百人一首の語呂合わせ一覧や覚え方についてまとめてご紹介していきますね。
さらに知りたい!百人一首の語呂合わせ一覧と覚え方
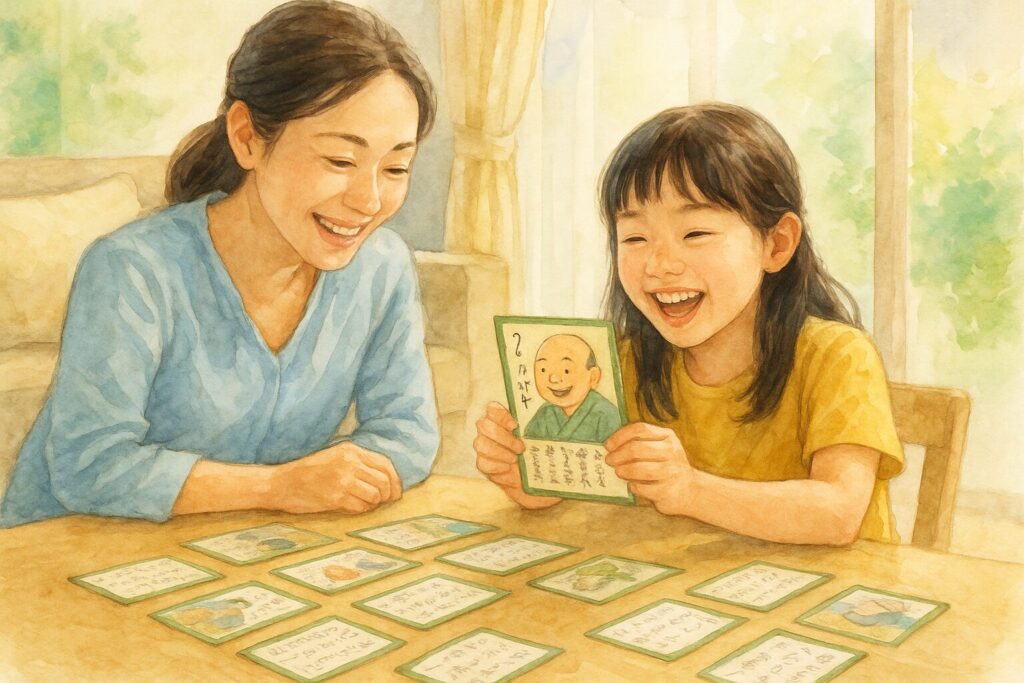
百人一首を覚えるときに、多くの人が悩むのが「どこから覚えればいいの?」ということではないでしょうか。
とくに初めて触れる方や、お子さんと一緒に楽しみたいママさんにとっては、和歌の言葉が古めかしく感じられて、なかなか覚えづらいと感じることもあるかもしれません。
そこで役立つのが、「語呂合わせ」という学びの工夫です。
語呂合わせとは、和歌の冒頭部分の音や意味を、覚えやすいフレーズや身近な言葉に置き換えることで、記憶に残りやすくする方法です。
たとえば、「うかりける 人を初瀬の 山おろしよ~」を「うっかりハゲ」と覚えるのは、まさにその代表的な例です。
一見ふざけているようにも思えますが、インパクトのある言葉ほど、記憶には強く残りやすいんです。
たとえば、「ちはやぶる」を「ちはやふる神話の竜田川」としてイメージすれば、自然と色鮮やかな場面が浮かびますし、「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の~」は「あしびき山」と略して山の風景とつなげると、印象に残りやすくなります。
また、「大江山 いく野の道の とほければ~」は「おおえのいくの道」で、「老えの行くの道」ともじって覚える、なんていう例もあります。
これは、おじいちゃんが山道を登っていく姿を思い浮かべると、意外と頭から離れないんですよね。
尚、こうした語呂合わせは、大人が使っても十分に効果がありますし、子どもと一緒に考えることで、おうち時間をちょっとした遊びに変えることもできます。
たとえば、私の友人は小学生の娘さんと一緒に「ママ語呂コンテスト」をしていたそうです。
「この和歌に面白い語呂をつけたら勝ちね」とルールを決めて、毎晩1首ずつ語呂合わせを作っていたら、自然と和歌も暗記できていたとのことでした。
こういう遊びの延長線にある記憶法って、とても理想的ですよね。
また、語呂合わせだけでなく、実際の札を机に並べて「早取り遊び」をするのも効果的です。
札を取る動作が加わることで、身体感覚と記憶がつながって、より強く覚えることができます。
更には、百人一首に出てくる自然の言葉――たとえば「雪」「風」「川」などといった単語を見つけて、それぞれの季節をイメージしながら覚えていくという方法もおすすめです。
これは、絵本の読み聞かせのように、視覚と感情をともなうことで記憶に深く残るからです。
ちなみに、最近では「百人一首 語呂合わせ一覧」と検索すると、多くの覚え方がネット上でも共有されています。
中にはアニメ風のキャラクターと組み合わせたものや、歌にメロディーをつけた覚え歌など、工夫されたコンテンツがたくさんあります。
そうした情報を活用すれば、無理に暗記しようとせずとも、日々の暮らしのなかで自然に和歌と親しむことができるはずです。
このように、百人一首の学びは「暗記」だけでなく「工夫」がポイントです。
それでは最後に、これまで見てきた内容をもとに、「はげ 百人一首」というテーマがどうしてここまで注目を集めているのか、今一度ふり返っていきましょう。
まとめ
「はげ 百人一首」というちょっとインパクトのある言葉に、最初は驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。
でも読み進めていくうちに、語呂合わせとしての「うっかりハゲ」が和歌の世界をぐっと身近にしてくれること、感じていただけたのではないでしょうか。
百人一首の魅力は、単に古典を学ぶだけではなく、心の動きや恋の葛藤、自然の美しさが、やさしい言葉とリズムに包まれて表現されているところです。
私たちが日々感じる「なんとなくモヤモヤする」「わかってほしいのに伝わらない」という気持ちも、実は千年前から同じようにあったのだと知ると、少し心が軽くなる気がします。
たとえば子どもとの関わりのなかで、思い通りにいかない気持ちや、誰にも言えない想いを抱えたときも、和歌の世界にふれることで、言葉にならない気持ちをそっと癒してくれることもあるかもしれません。
今回ご紹介した語呂合わせや学習アプリは、忙しい毎日のなかでも無理なく取り入れられる工夫ばかりです。
家族で楽しんだり、子どもの興味を引き出すツールとして活用したり、百人一首が「難しい」から「面白い」に変わるきっかけになればうれしいです。
これからも、和歌というちょっと不思議であたたかい世界を、気負わず楽しんでみてくださいね。
“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本
今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
参考記事
・はげ ちび 漢字|知らなかった意味と優しく受け止めるヒント
