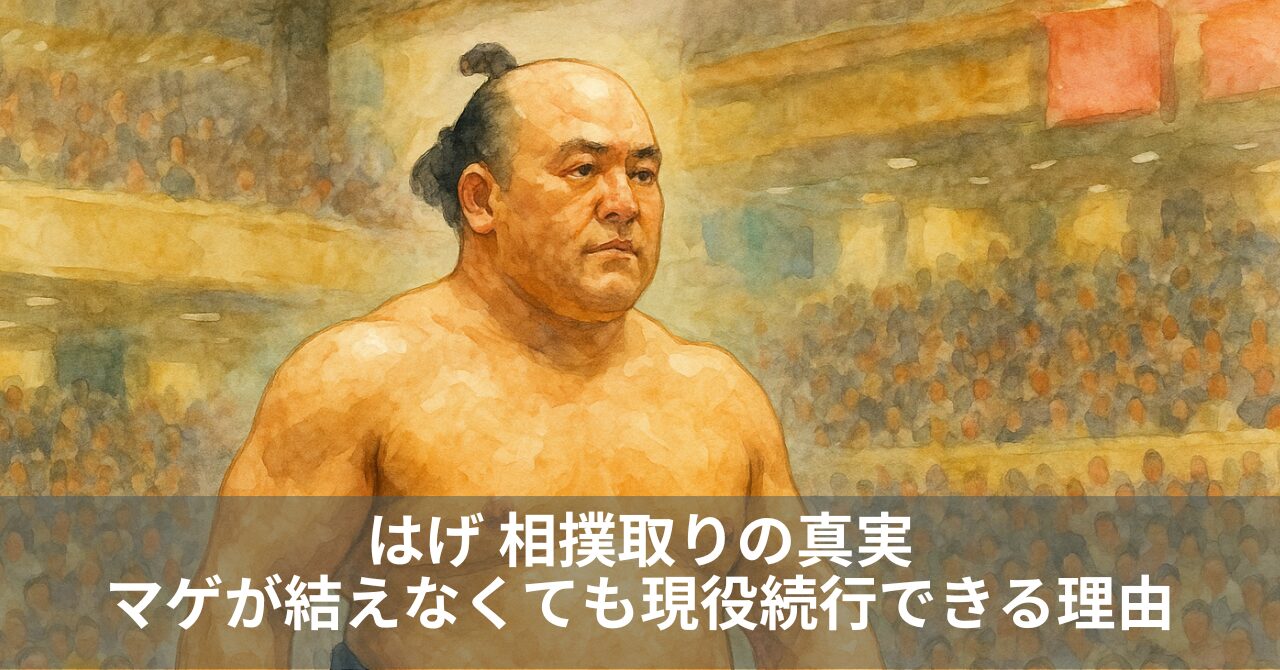相撲取り=ちょんまげのイメージ、ありませんか?
でも実は、「はげ 相撲取り」には深い事情があるんです。
マゲが結えないと引退という噂もありますが、60代男性髪型薄毛対策と同じように、相撲界でも工夫しながら続けている人が多いんですよ。
たとえば、60代男性髪型薄毛対策では分け目やセットで印象を変えますが、力士も補助毛などで対応しているんです。
この記事では、「はげ 相撲取り」の真実に迫りながら、薄毛でも自信を持って生きる力士たちの姿をご紹介します。
 Aya
Aya「“最近疲れてる?”って言われたその理由、頭皮だったかも。」
(心の声:髪があるだけで、こんなに若く見えるなんてズルい…)
男女兼用の本気の育毛剤
今なら13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー
→ 詳しく見る
- マゲで引退はルールでなく、本人の判断が多い
- 薄毛でも補助毛や工夫で現役を続ける力士も多い
- 髪型は格式と誇りの象徴、断髪式もその延長
- 見た目より努力や姿勢が力士の本当の魅力
力士はハゲたら引退しなければならないのか?都市伝説の真相
「マゲを結えなくなったら力士は引退しなければならない」という話を、一度は耳にしたことがあるかもしれません。
特に相撲に詳しくない方にとっては、「ちょんまげ=力士の象徴」というイメージが強く、それができなくなること=土俵に立てなくなる、という印象につながるようです。
でも実際には、それは都市伝説に近いものであり、現代の相撲界では必ずしもそうとは限らないのです。
なぜなら、マゲを結うための髪の長さや量が足りなくなっても、すぐに引退になるという明確なルールがあるわけではないからです。
たとえば、過去には脱毛症の影響で頭髪が非常に薄くなってしまった力士が、それでも現役を続けた事例があります。
有名な例としては、エジプト出身の大砂嵐関が挙げられます。
彼は髪を結えるほどの毛量がなかったにもかかわらず、関取として数年間活躍を続けました。
このように、外見的な条件だけで力士の進退が決まるわけではなく、成績や体調、本人の意思などが大きく関わってくるのです。
また、相撲は日本の国技として長い歴史を持つ競技ですが、同時に時代とともに少しずつ柔軟な対応も増えてきました。
かつては「大銀杏(おおいちょう)を結えない=関取ではない」という見方も根強くありましたが、現代ではウィッグのような補助的な方法や、髪型を工夫することで対応しているケースも存在します。
ちなみに、ちょんまげというと「江戸時代の武士」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実は相撲のちょんまげには独自の進化があり、力士の象徴として現在に至るまで受け継がれています。
また、横綱や上位の関取になると、土俵入りの際には立派な大銀杏を結いますが、これもまた髪の毛だけで作るのではなく、専門の床山(とこやま)が補助毛を使って整えることもあります。
ですから、「はげたら即引退」というのは、少し誤解を含んだ考え方だと言えるでしょう。
要するに、相撲界では見た目以上に実力や努力、人間性が重視される傾向があり、髪の毛が薄くなったからといって自動的に土俵を去らねばならないというルールは存在しないのです。
このあたりを誤解したままだと、ランキング上位の力士たちの努力や工夫を見落としてしまうことにもつながりかねません。
では次に、実際に薄毛で現役を続けた力士たちの実例を紹介していきます。
“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本
今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
薄毛でも現役続行!マゲが結えない力士たちの実例紹介
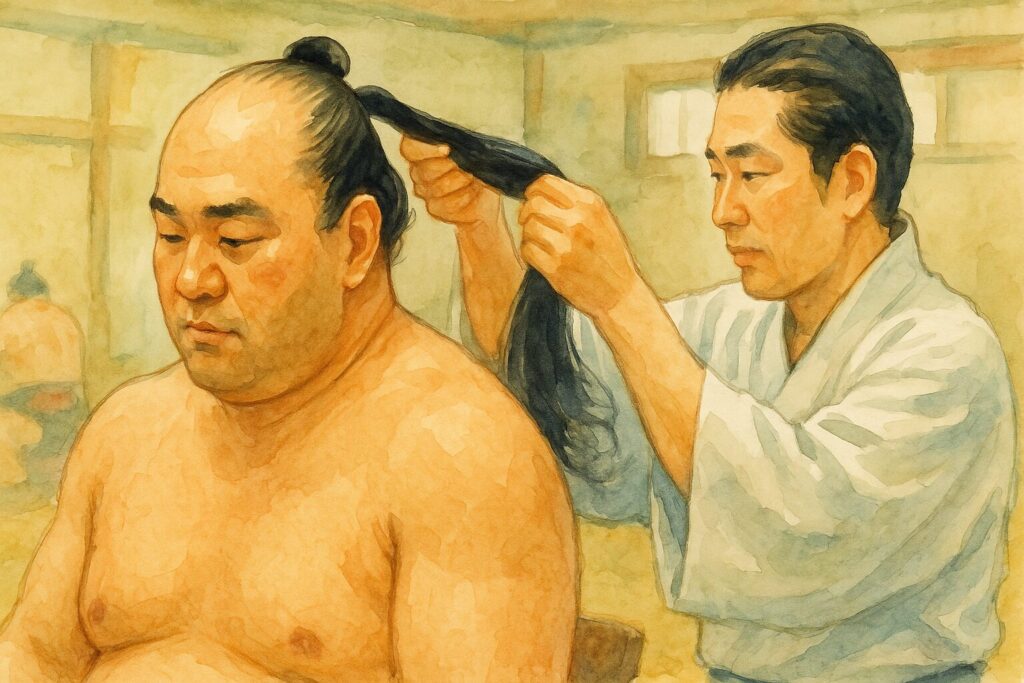
相撲の世界では「マゲ=力士の象徴」というイメージが強く、そのために「マゲが結えない=引退」という誤解が広まりやすいのだと思います。
しかしながら、現実にはマゲが結えなくても現役を続けている力士は存在します。
たとえば、元十両・大砂嵐関は、非常に毛量が少ないことで知られていました。
外国人力士ということもあり、もともとの髪質が日本人と異なり、髪を伸ばしてもなかなか結えるほどにはならなかったそうです。
それでも、彼は土俵での取り組みに一切妥協せず、堂々とした相撲を見せてくれました。
このように、髪型だけで力士の価値が決まるわけではないということを、大砂嵐関は実践で示していたと言えるでしょう。
また、ある床山さんの話によると、マゲが結えない場合には補助毛(つけ毛)を使って形を整えることもあるそうです。
これは、いわば力士版のエクステとも言える対応策で、マゲの形を維持しながらも見た目に配慮する方法です。
言い換えると、相撲界にも「見せ方」を工夫する柔軟さがあるということですね。
他にも、かつて幕下で活躍した力士の中には、若年性脱毛症のため20代で既に髪が後退していた方もいます。
そういった方々は、マゲの形にこだわるのではなく、力士としての強さや誠実な姿勢でファンの支持を集めてきました。
たとえば、子育て中のママが「この人かっこいいな」と思う基準も、見た目だけでなく、誠実さや一生懸命さに心惹かれることが多いのではないでしょうか。
同じように、相撲ファンにとっても、髪の毛の量よりも、どれだけ真剣に土俵に向き合っているかが評価の対象になります。
ちなみに、ランキング上位の関取たちの中にも、実はウィッグのような工夫をしている方がいるという話もあります。
もちろん公にはされていませんが、それだけ外見への気配りと競技力の両立に努力しているのです。
尚、マゲが結えなくなったことをきっかけに引退する力士もいますが、それはルールというよりも、自分の美学やけじめとして決めているケースが多いようです。
たとえば、あるベテラン力士は「自分のマゲが結えなくなったら、潔く引く」と話していたそうですが、これはあくまでその人自身の判断です。
つまり、マゲの有無は力士のキャリアを左右する絶対条件ではなく、最終的にはその人がどうありたいかによって決まるのです。
このように考えると、薄毛で悩むことがあっても、それが即座に「終わり」を意味するわけではないと安心できますよね。
では次に、相撲界で大切にされているちょんまげや大銀杏といった髪型の文化について、もう少し深掘りしていきましょう。
相撲界の髪型事情:ちょんまげと大銀杏の文化的背景
相撲と聞くと、まず思い浮かべるのが「ちょんまげ」ではないでしょうか。
大柄な力士がちょんまげを結って土俵でぶつかり合う姿は、日本文化を象徴するひとつの風景とも言えます。
けれど、その「ちょんまげ」にも深い意味と歴史があることは、意外と知られていないかもしれません。
そもそも相撲界の髪型は、単なるスタイルではなく「伝統」と「格式」のあらわれです。
ちょんまげの起源は江戸時代の武士にさかのぼります。
当時は、頭頂部を剃って周囲の髪を結い上げることで、兜をかぶりやすくする実用性がありました。
その文化が武士階級の象徴として広まり、やがて明治維新の時代になると、断髪令により一般的には廃れていきます。
しかしながら、相撲界ではその様式を残し、独自の発展を遂げてきたのです。
力士が髪を伸ばして結うちょんまげは、見た目のためだけでなく、地位や覚悟を象徴する役割を持っています。
特に、関取以上の力士が結うことが許される「大銀杏」は、いわば相撲界における勲章のような存在です。
その形はまるで扇のように広がっていて、土俵入りの際には非常に華やかで目を引きます。
この大銀杏は、専門の床山によって時間をかけて丁寧に結われます。
たとえば、朝早くから始まる取組の前には、床山さんが2時間以上かけて、一本一本の毛を整えながら形を作っていくのです。
これは、美容室で七五三の日本髪を結ってもらうような、まさに儀式に近い丁寧さです。
ちなみに、関取になる前の力士たちは「丁髷(ちょんまげ)」のスタイルで過ごしますが、この段階でもしっかりとした手入れが求められます。
髪が健康でなければ美しく結えないため、日々の洗髪や整髪はとても重要なのです。
また、ちょんまげや大銀杏の存在は、力士を一目で「相撲取り」と認識させる記号でもあります。
道で力士を見かけた時、その髪型だけで「お相撲さんだ」とわかるように、文化的アイコンとしての役割も担っているのです。
それに対して、現代の多くのスポーツ選手は自由な髪型が主流ですよね。
たとえば、プロ野球選手やサッカー選手が金髪にしたり、刈り上げスタイルにしたりするのと比べると、相撲界の髪型には「統一感」と「厳格さ」が残っています。
これは、相撲が単なるスポーツではなく「儀式性」を伴う武道の一種であることを表しているのかもしれません。
更には、力士の髪型はファンにとっての楽しみのひとつでもあります。
たとえば「今日の○○関の大銀杏、きれいに決まってたね」といった会話が、観戦後のお茶の間で交わされることもあります。
このように、髪型ひとつとっても、力士の世界には深い意味と伝統が詰まっているのです。
では次に、もしその大切な髪型をほどいたらどうなるのか、力士の髪に関するルールや慣習について見ていきましょう。
マゲをほどいたらどうなる?力士の髪型に関するルールと慣習
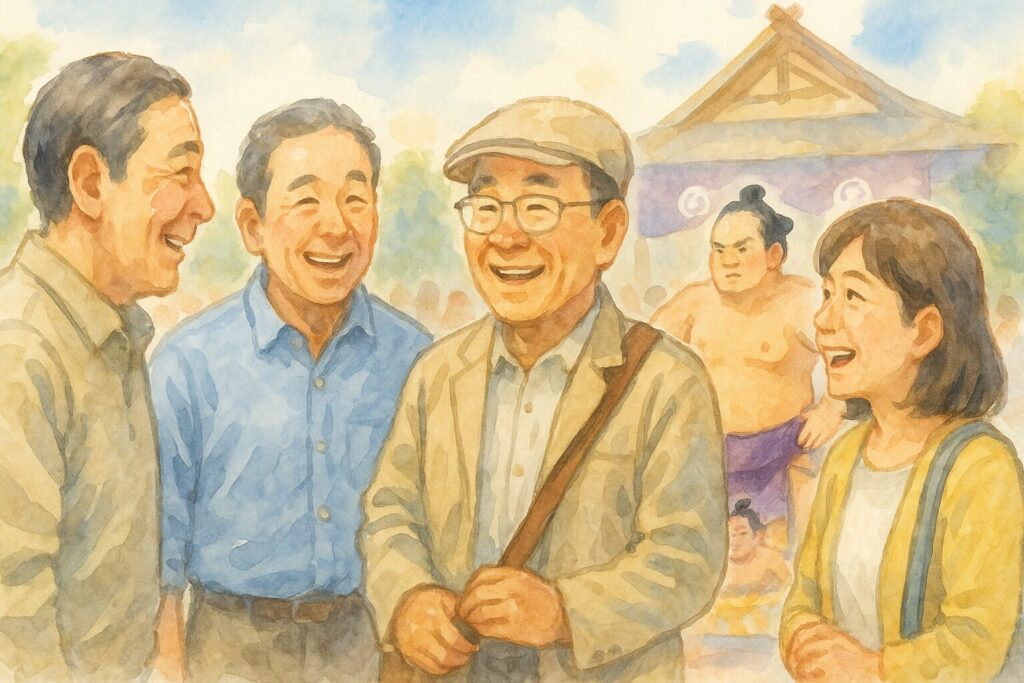
相撲の世界では、髪型には厳格な決まりごとが存在します。
けれども、「マゲをほどいたら即引退」や「土俵に立てない」といった話には、少し誤解が混ざっているようです。
たしかに、土俵入りや取組などの正式な場面では、マゲをきちんと結っていることが求められます。
しかしながら、マゲをほどいた状態がすぐにルール違反になるわけではありません。
たとえば、移動中や宿舎での時間には、髪を下ろしている力士もいます。
つまり、マゲは常に結っていなければいけないという決まりではなく、場面に応じた使い分けがされているのです。
ただし、力士として土俵に上がるときには、マゲの形はとても重要になります。
特に、関取になると「大銀杏」を結うことが義務とされ、その姿が相撲の格式や誇りを表しています。
この「結うことが義務」というのは、強制的なルールというより、格式にふさわしい見た目を整えるという慣習に近いものです。
たとえば、七五三や結婚式で、着物に合わせて髪型を整えるようなものですね。
一方で、マゲが結えなくなった場合については、決まりは曖昧です。
昔は「マゲが結えなくなったら引退」という価値観が強かったのですが、現在では柔軟な対応が増えています。
脱毛や病気などで髪が薄くなった力士の場合、補助毛や形を工夫することで土俵入りを続ける例もあります。
これは、本人の意思や土俵への情熱を尊重する相撲界の姿勢の表れとも言えるでしょう。
ちなみに、引退相撲では「断髪式」が行われ、マゲを切る儀式が執り行われます。
これは力士人生の締めくくりとして、本人や親方、ファンにとっても非常に感慨深い瞬間です。
言い換えると、マゲは「髪型」以上の存在であり、力士のキャリアそのものを象徴するものでもあるのです。
更には、髪型には日々の積み重ねも必要です。
毎日の髪の手入れや床山との信頼関係、さらには取組後の汗を拭いたあとの整髪まで、すべてが「土俵に立つ準備」としての役割を果たしています。
つまり、マゲをほどいた状態というのは、「準備中」や「オフの時間」として捉えられているだけで、特別な問題行動ではないということです。
尚、一般社会で例えるなら、スーツ姿でのプレゼンが終わった後にネクタイを外すようなものかもしれません。
きちんとした場では整えた姿が求められるけれど、常にその形でいなければならないというわけではないのです。
それでは次に、こうした厳しい髪型の決まりに対応するため、薄毛力士がどんな対処法をとっているのかを見ていきましょう。
薄毛力士のための対処法:現代の相撲界における対応策
相撲の世界では、ちょんまげや大銀杏といった髪型が力士の象徴とされてきました。
そのため、薄毛になった場合の対処法は、とても繊細で大切なテーマとなります。
けれども、現代の相撲界では、この問題に対して柔軟な対応が進んでいるのです。
まず、ひとつ目の対処法として挙げられるのが「補助毛(つけ毛)」の使用です。
これはマゲを結うための髪のボリュームが足りない場合に、床山さんが自然に見えるように毛束を足してくれる技術です。
たとえば、ちょうど日本髪を結うときに使う「かもじ」に似たような存在で、本人の髪に混ぜながら大銀杏の形を整えていきます。
このような対応によって、力士の威厳や見た目の美しさが保たれているのです。
次に挙げられるのが、「髪型の工夫」です。
髪が薄いからといって必ずしもマゲが結えないとは限らず、毛流れの方向を整えたり、分け目を工夫したりすることで、きちんとした見た目を保つことができます。
たとえば、女性でも産後の抜け毛が気になる時期に、ヘアアレンジやスプレーでボリュームを出して対応することがありますよね。
それと同じように、力士たちも自分なりの工夫を重ねながら土俵に立っているのです。
また、床山との信頼関係も非常に重要です。
髪の状態や量、質は力士によってさまざまであり、それを見極めながら毎回最適な形に仕上げるのが床山の役目です。
尚、床山は「相撲部屋のヘアスタイリスト」ともいえる存在で、毎日多くの力士の髪を扱いながら、それぞれの個性や状態に合わせて丁寧に整えてくれます。
言い換えれば、力士と床山の二人三脚によって、髪型の美しさは支えられているのです。
さらに、食生活や生活習慣の見直しも対処法のひとつです。
力士は体重を増やす必要があるため、脂質や糖質の多い食事が中心になりがちですが、栄養バランスが偏ると髪や頭皮にも影響が出てきます。
だからこそ、部屋によっては栄養士のサポートを取り入れて、髪にもよい影響を与える食事を取り入れているところもあります。
ちなみに、薄毛に悩む一般の方にも参考になる話として、和食中心の食生活や適度な運動、睡眠の質を上げることは、髪の健康にとても効果的だと言われています。
このように、相撲界の薄毛対策は見た目を保つ工夫と、内側からのケアがバランスよく組み合わさっています。
そして何よりも大切なのは、力士本人の「土俵に立ち続けたい」という強い気持ちです。
たとえ髪が薄くなったとしても、それを理由に諦めるのではなく、工夫と努力で乗り越えていく姿勢が、相撲の本質とも言えるのではないでしょうか。
では次に、そんな力士たちがどのようにして引退を決意するのか、髪型との関係を含めて過去の事例を交えながら見ていきましょう。
力士の髪型と引退の関係:過去の事例とその影響
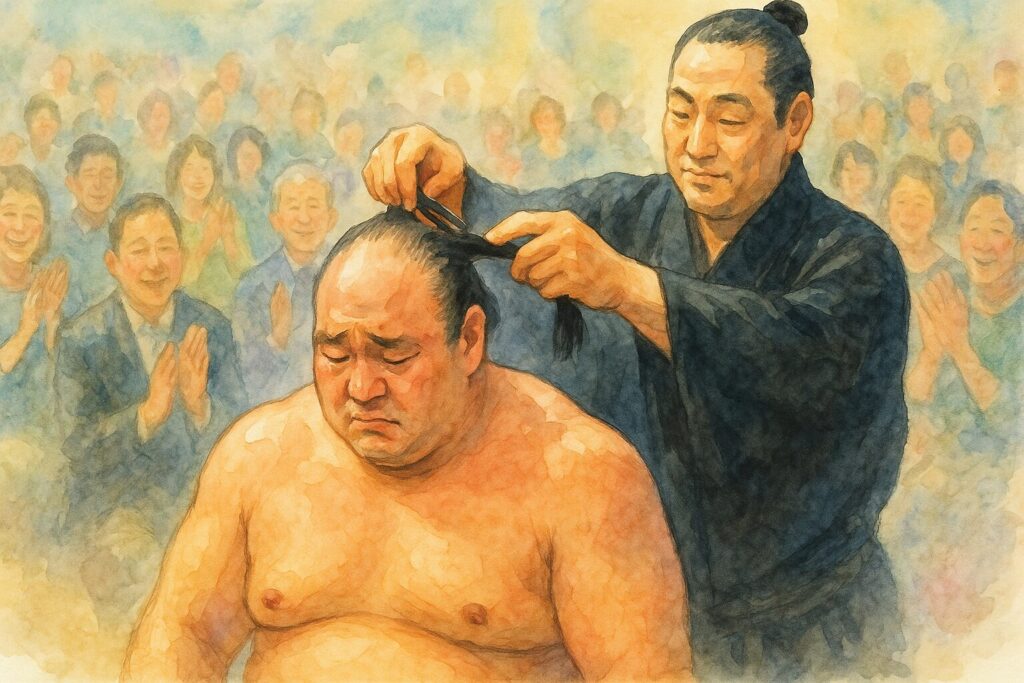
力士にとって「引退」というのは、相撲人生の大きな節目であり、本人はもちろん、部屋の仲間やファンにとっても非常に重い出来事です。
特に、髪型と引退には密接な関係があると信じられてきました。
けれど、現代ではその考え方にも少しずつ変化が生まれてきています。
たとえば、「マゲが結えなくなったから引退した」という話は、かつての相撲界ではよく語られていました。
ただし、それはあくまで本人の意志によるケースが多いようです。
髪が薄くなってマゲが結えなくなったからといって、相撲協会が「では引退してください」と告げることはありません。
むしろ、「そこまでやったのだから、もう潔く引こう」と自ら決断する力士の姿に、周囲も尊敬の念を抱くことがあるのです。
たとえば、ある関取経験者はインタビューで、「マゲが立派に結えなくなった自分を、子どもに見せたくなかった」と語っていました。
このように、見た目や伝統を大切にしたいという思いが、引退の決め手になることもあるのです。
また、引退の儀式である断髪式では、本人のマゲを多くの関係者や恩人が少しずつ切っていき、最後に師匠がバッサリと切り落とします。
これは、髪型を通じて築き上げてきた相撲人生を区切る、とても象徴的な儀式です。
例えるなら、卒業式に制服のボタンを渡すような、涙と笑顔が交錯する時間です。
ちなみに、断髪式にはファンも参加できることがあり、その力士をずっと応援してきた人にとっては、思い出に残る特別な日となります。
尚、この式をもって完全に「お相撲さん」から離れるわけですが、中には引退後も相撲部屋に残り、指導者として後進の育成に尽力する人もいます。
その際は、当然マゲはありませんが、力士として培った姿勢や哲学は変わることなく受け継がれます。
更には、力士が引退後に髪を伸ばし、一般のヘアスタイルに戻ることを楽しみにしているケースもあります。
「普通の美容室に行ってみたい」「好きな髪型にしたい」という声を聞くと、こちらとしてもクスッと共感してしまいますよね。
毎日家事や育児に追われているママさんたちも、「今日は髪を整える余裕がないな」と思う日もあると思います。
けれど、少し髪型を変えるだけで気分が明るくなることってありますよね。
力士にとってのマゲも、それに似たような「心の支え」なのかもしれません。
つまり、髪型が整わなくなった時、それは単なる外見の問題だけでなく、自分らしさや誇りの象徴が崩れる感覚なのかもしれません。
だからこそ、引退という決断をしたくなるのだと思います。
そして、そんな背景があるからこそ、薄毛と向き合いながら現役を続ける力士たちには、いっそうの敬意が集まるのです。
このように、髪型と引退はただの見た目の問題ではなく、その人の相撲人生の歩みと深くつながっていることが分かります。
それでは最後に、この記事全体のまとめをご紹介いたします。
まとめ
相撲取りと髪型って、実はとっても深い関係があるんです。
「マゲを結えなくなったら引退」なんて聞くと、まるで髪が力士の全てみたいに思えてしまいますが、今の相撲界ではそこまで単純な話ではありません。
実際には、薄毛になっても工夫しながら土俵に立ち続けている力士がたくさんいます。
補助毛を使ったり、分け目や毛流れを工夫したり、さらには床山さんとの信頼関係で見た目を整えたりと、その対応はとても丁寧で真剣なんです。
この姿勢って、私たちの暮らしにもどこか重なりませんか?
たとえば、出産や育児を経験して、自分の見た目がちょっと変わったとき。
それでも「今の自分も素敵」って思えるように、少しずつできることから整えていく。
力士たちの姿も、そんな風に感じられて、なんだか励まされるような気がします。
また、引退を決める理由も、決してルールに縛られているわけではなく、自分なりの区切りや誇りを大切にしているんですね。
だからこそ、髪型だけじゃなく、どれだけ努力して土俵に立ち続けたか、その生き方すべてが力士の魅力なんだと改めて気づかされます。
私たちも、毎日の小さな積み重ねが、自分らしさにつながっているんですよね。
“男女兼用頭皮環境を整える正しい使い方自宅でサロン超えの手触りが叶う1本
今なら公式サイトで13,640円→1,980円、90日返金保証付きで安心デビュー!
(心の声:年齢も性別も超えて…この1本で“私もアリ”って言える髪になる。)
参考記事
・薄毛坊主後悔する人の共通点とは?似合わない理由と対策を徹底解説